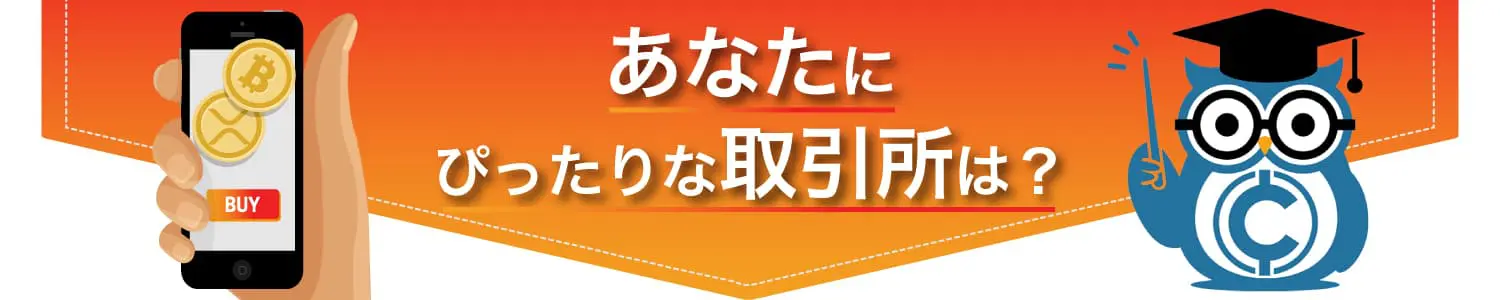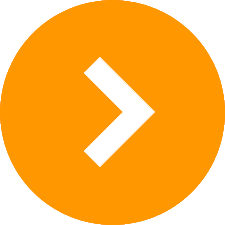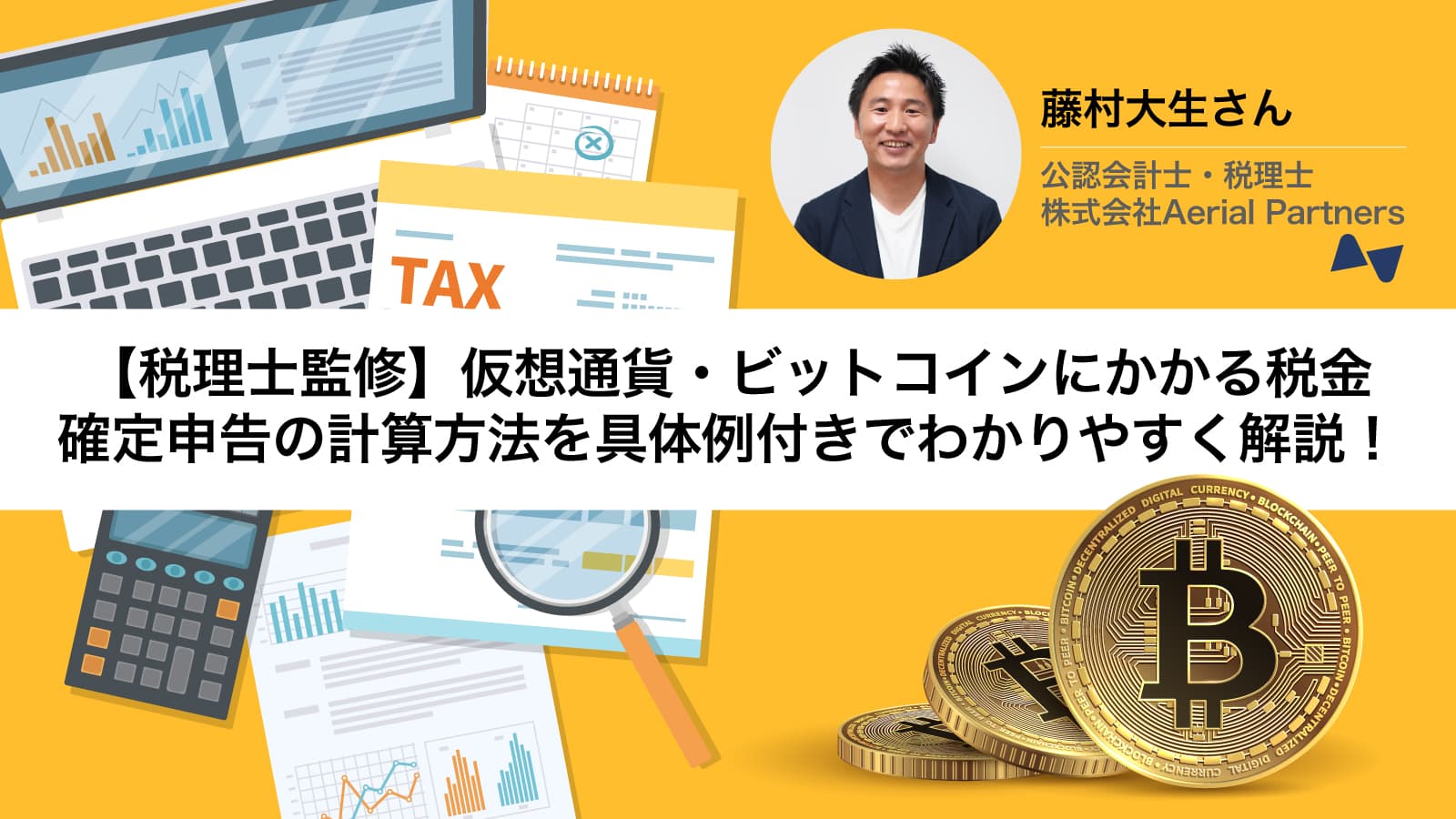仮想通貨の法律規制って?法律に基づく定義や規制、税金などを簡単に解説!
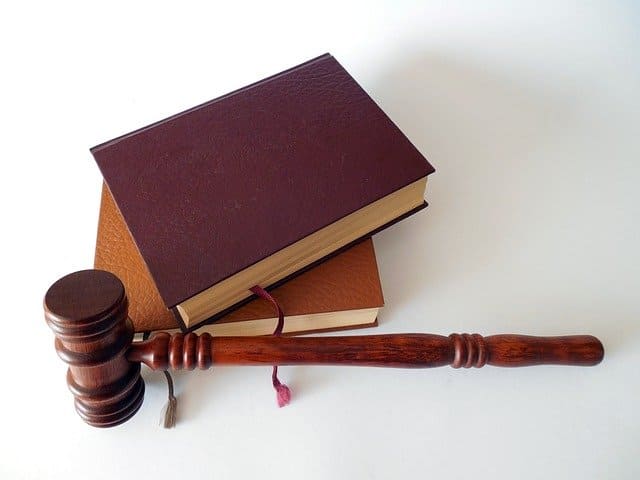
「暗号資産(仮想通貨)の法律って結局何がいいたいんだ・・・?」と、お悩みではありませんか?
どんな形であれ、暗号資産(仮想通貨)を扱っていて不安になるのが、「法律」の問題ですよね。刑事罰の対象でもあることから、「知らなかった」では済まされません!
見て見ぬ振りをするのではなく、知っておく必要があるのですが、条文は難解な法律用語だらけ・・・。
そこで!今回は国内の暗号資産(仮想通貨)に関する法律、いわゆる「暗号資産(仮想通貨)法」をコインパートナーが分かりやすく解説します!
金融庁の暗号資産(仮想通貨)・取引所に対する認識や、海外との比較、気になるQ&Aまで、難解な言葉を噛み砕いて説明しているので、これを読んで暗号資産(仮想通貨)法を理解しておきましょう!
仮想通貨の法律「仮想通貨法」とは?

暗号資産(仮想通貨)の市場の急激な拡大に伴って、日本政府は急いで法規制を進めています。
これからの市場の分析や、暗号資産(仮想通貨)そのものの未来を考えるためにも、現実的な法律の内容を知っておくことは欠かせません。
ここでは、そのわかりにくい暗号資産(仮想通貨)の法律について簡単に説明します!
「暗号資産(仮想通貨)法」とは

厳密には、日本の法律の中に「暗号資産(仮想通貨)法」というものはありません。なので、いわゆる「暗号資産(仮想通貨)法」とは、
- 暗号資産(仮想通貨)に関する国内の法律の総称
- 「改正資金決済法 第3章の2 暗号資産(仮想通貨)」の内容
のどちらかのことを指しています。
①については、金融庁が公開している、こちらのページ(金融庁公式)で、随時確認することができます。
①の中でも特に、2017年4月1日に有効化された、日本で最初の暗号資産(仮想通貨)に関する法律が②の改正資金決済法です。
「改正資金決済法」とは

いわゆる「改正資金決済法」とは、「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案」で提案された、「資金決済法の改正案」のことをいいます。法律案全体は、金融庁が公開しているこちらのページ(金融庁公式)で確認することができ、このうち106~149ページが特に暗号資産(仮想通貨)に関係する部分となります。
ここで具体的に述べられていることは大きく以下の2つに分かれます。
- 暗号資産(仮想通貨)の定義
- 暗号資産(仮想通貨)交換業の定義と規制
法律によって定められる「仮想通貨」の定義

改正資金決済法第二条5項において、従来の電子マネーなどと比較して、具体的にどういったものが「暗号資産(仮想通貨)」として定義されるのか明文化されました。一号、二号のいずれかに分類されるものは暗号資産(仮想通貨)とみなされ、法律の規制対象となると同時に、どちらにも属さないものは暗号資産(仮想通貨)とはみなされません。
改正資金決済法 第二条
5項 この法律において「暗号資産(仮想通貨)」とは、次に掲げるものをいう。
一号 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二号 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
Source: https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=421AC0000000059#N
一号、二号がそれぞれ何を言っているか、言葉を噛み砕いて説明します。
一号暗号資産(仮想通貨)

一号で述べられている暗号資産(仮想通貨)の条件は、以下のように分けることができます。
- 不特定の相手と、物品の購入・借り受け・サービスに対する弁済のために使えること。(決済手段として使える)
要するに、それを用いて相手を特定せず広く一般的にものやサービスの代金支払いが自由にできるか、ということです。
- 不特定の相手と、売買ができる財産的価値
これは、そのもの自体が普遍的な財産的価値を有しており、あらゆる市場参加者と自由に売買できるものである、ということです。
- 電子機器などに、電子的方法によって記録されており、電子的処理によって移転できること。
簡単にいうとコンピュータを使って、インターネット上でやりとりできるか、ということです。
- 本邦通貨(円)・外国通貨・通貨建資産(後述)でないこと。
日本円やドルなどの法定通貨と別の価値基準を持っているという意味です。
これら4つ全ての条件を満たしているもののみが暗号資産(仮想通貨)とみなされます。
ビットコインがこれらの条件を全て満たしていることを考えると、一号で掲げられた暗号資産(仮想通貨)をイメージしやすいと思います。
二号暗号資産(仮想通貨)

二号で述べられている暗号資産(仮想通貨)の条件は、以下のように分けることができます。
- 不特定の相手と、一号で定義された暗号資産(仮想通貨)と、相互に交換ができる財産的価値。
- 電子的処理によって移転できること。
これは、決済手段としては満たされていなくとも、不特定の人を相手に、一号暗号資産(仮想通貨)であるビットコインなどと電子的処理を介して交換することのできるものは暗号資産(仮想通貨)としてみなされることを示しています。
日本円との取引が盛んでないアルトコインについても、一号暗号資産(仮想通貨)との交換が可能であれば、暗号資産(仮想通貨)としてみなされます。
Suicaなど電子マネーとの違い

暗号資産(仮想通貨)は、デジタル管理された資産であり、SuicaやTポイントなどといったものと混合されがちですが、電子マネーと暗号資産(仮想通貨)は全く異なります。
一号の条件の中に、「通貨建資産」という言葉が出てきました。通貨建資産とは、法定通貨で金額表示され、法定通貨基準でやりとりが行われる資産のことを言います。ゆえに、いわゆる電子マネー(前払式支払手段)は通貨建資産とみなされます。
通貨建資産は一号暗号資産(仮想通貨)の定義から外されています。また、Tポイントなどは不特定の人とのやりとりを行うことができません。したがって、電子マネーや電子ポイントは暗号資産(仮想通貨)とは全く異なるものです。
ビットコインなどのいわゆる暗号資産(仮想通貨)は、それ自体が通貨としての価値を持ち、日本円もしくはドル表示を媒介としない取引が行われることから、通貨建資産としてはみなされません。
「仮想通貨交換業」について

改正資金決済法第二条7項においては、bitFlyerなどのいわゆる暗号資産(仮想通貨)取引所を、「暗号資産(仮想通貨)交換業」と命名し、その定義と規制を行なっています。ここでは、それらの説明に加え、最新の取引所に対する規制の状況を解説します。
「暗号資産(仮想通貨)交換業」の定義

改正資金決済法において、暗号資産(仮想通貨)交換業は次のように定義されました。
改正資金決済法 第二条
7項 この法律において「暗号資産(仮想通貨)交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産(仮想通貨)の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいう。
一号 暗号資産(仮想通貨)の売買又は他の暗号資産(仮想通貨)との交換
二号 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
三号 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭又は暗号資産(仮想通貨)の管理をすること。
Source: https://www.fsa.go.jp/common/diet/190/01/shinkyuu.pdf
一号の、「暗号資産(仮想通貨)の売買又は他の暗号資産(仮想通貨)との交換」とは、販売所がユーザと行なっているような、暗号資産(仮想通貨)の売買や交換のことを言います。暗号資産(仮想通貨)交換業者とユーザが直接的にやりとりします。
二号の、「一号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理」とは、取引所の板取引のような、ユーザの代わりに暗号資産(仮想通貨)の売買や交換のことを言います。二号があることによって、取引所未登録の業者が、既存の取引所を利用して交換業を行うことを防いでいます。
三号の、「一号二号に関して、利用者の金銭又は暗号資産(仮想通貨)の管理をすること」とは、その文面通り取引所利用者の暗号資産(仮想通貨)、法定通貨を管理することを言います。
要するに、「暗号資産(仮想通貨)取引に関わる事業」をしている業者のことを暗号資産(仮想通貨)交換業としてみなしています。このような定義に含まれる業者のうち、内閣総理大臣による登録審査に認められた業者のみが、法に則って取引所として機能することができます。
暗号資産(仮想通貨)交換業者への規制

取引の最低限の安全性を保つために、取引所の審査に関してはいくつかの条件があります。(改正資金決済法第63条5項および、暗号資産(仮想通貨)交換業者に関する内閣府令)
主な条件については以下のようなものがあります。
- 株式会社もしくは、日本に支社がある海外取引所のうち国内代表者を持つものであること。
すなわち、どこかしらの国が、既にその業者の信頼性を認めているかということです。海外取引所が日本進出を目指すのは、この要件を満たせているか問題ありません。
- 暗号資産(仮想通貨)交換業を円滑に行うに足る財産的基礎を有していること。
具体的には、資本金の額が1000万円以上であり、純資産額がマイナスではないことを指定しています。暗号資産(仮想通貨)の取引を円滑に行い、かつ、セキュリティ面で適切な投資を行うことができることを保障できる程度の資本が必要です。
- ユーザの誤った判断を防ぐ、正確な情報の提供義務
事業者は必然的にユーザよりも情報が多くなります。暗号資産(仮想通貨)市場はまだまだ信頼のおける情報源が少なく、情報が偏ったままだと、ユーザは適切な判断を行うことができなくなり、リスクが大きくなってしまいます。したがって、取り扱い通貨の概要や、価格変動リスクなど、ユーザに正しい理解を促すような情報提供をする必要があります。
- 法を守るための体制を有していること。
暗号資産(仮想通貨)は、マネーロンダリングに使用される可能性を常に孕んでおり、そういった違法に対する対策を行う必要があります。本人確認の徹底や、疑わしい取引の届出義務などが義務付けられています。
- 他の取引所や、暗号資産(仮想通貨)と誤認されるような名称でないこと。
少し変わった観点ですが、要するに、例えば「円」っぽい名前や、「bitFlyer」っぽい名前にしたりと、誤認を誘うような名前を付けないように、ということです。
- 他国での登録取り消しを受けていた場合、そこから少なくとも5年以上経っていること。
他国で信頼を失った場合、日本でも認められません。
- 他事業で公益に反することを行なっていないこと。
暗号資産(仮想通貨)取引によって得た利益を用いて違法行為を行う場合、当然その暗号資産(仮想通貨)取引自体をやめさせる必要があります。
こうした条件を満たした上で、金融庁による審査を受けます。
審査に通った場合でも、上のような審査項目を満たしているか、常に国の監督の下で事業を行う必要があります。必要によっては、立入検査、業務改善命令などに加え、登録の抹消、最悪の場合刑事罰が与えられます。
しかしながら、審査や規制に関して、まだ確実と言える判断基準はなく、事例に即して考えられます。これから事業を行おうと思っている方は、管轄の税務署に判断を求めることを強くお勧めします。
最近の規制情報

上述の暗号資産(仮想通貨)交換業者として認めらるための条件を満たし、審査で認められた国内登録業者は、bitFlyerやZaifなど、たった16社しかありません(暗号資産(仮想通貨)交換業登録業者(金融庁公式))。
その他に「みなし業者」と呼ばれる取引所があります。みなし業者は、改正資金決済法が施行された時点で既に暗号資産(仮想通貨)取引を事業として行なっていた取引所のことをいい、一時的に交換業が認められています。
みなし業者に対する監視の姿勢は強く、マネーロンダリング対策を行わなかったあるみなし業者に対して、強制的に業務停止命令を与えた事例もあります。
2018年5月には日本経済新聞の取材により、金融庁の今後の登録方針が明らかになりました。これまでの育成方針から打って変わって監視を強め、審査の基準も厳しくする姿勢を示しました。重点5項目に沿って運営体制を調べるとしており、具体的には以下の項目が挙げられます。
- 顧客と業者との資産分別管理の徹底
- 内部管理体制の強化、株主と経営の分離、システム開発と管理の分離
- コールドウォレット(暗号資産(仮想通貨)のオフライン保管)、マルチシグ(秘密鍵の複数化)の導入
- マネーロンダリングに使用される可能性の高い匿名性通貨を原則認めない
これらは、取引所の内部不正や外部からの攻撃を防ぎ、安全性を高めるための手段です。
また、2020年1月には金融庁が暗号資産(仮想通貨)取引のレバレッジ倍率を2倍までとする方針を発表しました。
これは主に投資家保護を目的としており、2020年の春には施行される予定となっています。
仮想通貨法の施行でどんな影響があるのか

暗号資産(仮想通貨)法を施行することによって、暗号資産(仮想通貨)は国に正式に決済手段として認められたことになります。
これにより安心感を持って暗号資産(仮想通貨)を利用することができるようになります。
また、暗号資産(仮想通貨)取引所が登録制になり、金融庁の監視下に置かれたことで、信頼性と安全性が格段に上がりました。
ユーザーを保護するための制度も整いつつあり、より暗号資産(仮想通貨)が一般の人にとって身近な存在になっていると言えます。
仮想通貨の法律について日本と海外を比較
 日本は海外と比べて、暗号資産(仮想通貨)に対して比較的寛容であると言われています。しかしながら、法規制についてはまだまだ進んでいないというのが現状です。
日本は海外と比べて、暗号資産(仮想通貨)に対して比較的寛容であると言われています。しかしながら、法規制についてはまだまだ進んでいないというのが現状です。
ここで、海外の大国の規制と比べてみましょう。世界的にどの国がどのような姿勢を示しているのか、こちらのサイト(ビットリーガル)参考にすることができます。
州によって大きく異なるアメリカ

アメリカは世界の金融街とも言われるウォール街を有し、金融市場に大きな影響を及ぼす力を持っています。そんなアメリカは比較的暗号資産(仮想通貨)に対して友好的と言われています。
しかしながら、アメリカは50の州全てに対して自治権が認められており、州によって規制状況が大きく異なるというのが現状です。bitFlyer社も参戦しているニューヨーク州は特に規制が厳しいとして知られています。
また、イーサリアムを有価証券として認めるかといった議論も起こりました。
議論の続くロシア

ロシアはその寒冷な気候と、近隣の中国のマイニング規制から、マイニング大国となっています。暗号資産(仮想通貨)やICOを全面的に禁止したい中央銀行と法整備を整えて推進したい財務省のせめぎ合いが続いています。
また、SNSアプリに対して否定的であるため、TelegramやLinkedinなどのアプリが既に禁止されています。これらのSNSは暗号資産(仮想通貨)開発者たちのコミュニケーションツールとして使われているため、ロシア国内における開発は下火となることが予想されます。
極めて否定的な中国

中国政府は暗号資産(仮想通貨)取引に関して極めて否定的な姿勢を示しています。政府に対する不安から、人民元から暗号資産(仮想通貨)に資産を移してしまう傾向が生まれやすいからです。暗号資産(仮想通貨)取引所やICO、マイニングに対して強い規制をかけています。
しかしながら、取引所やマイニングに関しては、大手企業は海外に拠点を移し、今もなお大きな影響力を持っています。
仮想通貨の法律についての気になるQ&A

どうして法規制が行われるの?
暗号資産(仮想通貨)は、もはやマイナーな遊びではなく、法定通貨に変わる第二の決済手段として認められつつあります。
Mt.Goxやcoincheckなどの流失被害を受けて、国民を暗号資産(仮想通貨)に関するリスクから守ると同時に、法定通貨が使われなくなることで失われた税収入を確保するために、国としては法規制せざるを得ません。
現実的な権力を持った国家によって、怪しいイメージを持たれがちな暗号資産(仮想通貨)を明確に定義し、不安定であった市場が安定化されることで、暗号資産(仮想通貨)に対するイメージが改善しさらに規模が大きくなることが期待されます。
暗号資産(仮想通貨)の税金・税制はどうなるの?
暗号資産(仮想通貨)に関する税制については、まだ明記されているわけではなく、国税庁による従来の法令の解釈によって定められています。基本的には、ほとんどの場合について課税対象となります。
暗号資産(仮想通貨)の税金について詳しくはこちら
消費税
暗号資産(仮想通貨)の売買取引については、2017年7月1日より消費税は非課税となっています。
しかしながら、ビックカメラで導入されているような、日本円の代わりに暗号資産(仮想通貨)で支払うような決済手段としての取引においては、通常日本円で課される消費税分の暗号資産(仮想通貨)を、その時のレートに従って支払う必要があります。
すなわち、従来の日本円と全く変わりません。
所得税
暗号資産(仮想通貨)について、発生しうる利益として、以下の2パターンが考えられます。
- 暗号資産(仮想通貨)取引による差額利益
- マイニングによる利益
- 暗号資産(仮想通貨)決済による収入
- 暗号資産(仮想通貨)のフォークによる新たな暗号資産(仮想通貨)の取得
1の差額利益は、利益確定した時点で所得としてみなされ、所得税の対象となります。
2のマイニング利益は、マイニングによって取得した時点で所得としてみなされ、マイニングにかかったコストを差し引いて、所得税の対象となります。
3の暗号資産(仮想通貨)決済による収入は、所得税の課税対象となります。
4のフォークによる収入は、そこで取得した通貨を利益確定した時点で所得としてみなされ、所得税の対象となります。
相続税
暗号資産(仮想通貨)が資産的価値を持つことは改正資金決済法で定義されているため、相続税の対象となることは国税庁により明言されています。
しかし、まだまだ議論の余地があり、法規制が追いついていない状況なので、詳しくは言及できません。
ホワイトリストって何?
ホワイトリストというものは、国によって正式に明言されている訳ではありません。厳密には「金融庁が認めた取引所が扱う暗号資産(仮想通貨)の一覧」を広くホワイトリストと呼んでいます。
裏を返せば、ホワイトリスト入りしていない通貨は、国内取引所で取り扱うことができません。
ホワイトリストについて詳しくはこちら
ICOはどういう扱いになるの?
現行の暗号資産(仮想通貨)の取引に加え、大きな金額が動く市場としてICOがあります。
もちろん上手くいった場合は大きな利益をあげることができますが、同時に価格下落可能性が大きいだけでなく最悪の場合完全に詐欺であることもあり、極めてリスクの高い取引です。
にも関わらず過度な広告や宣伝が行われており、こうした背景から金融庁はICOに対しても法規制を行なっています。
また、ICOに対する金融庁の見解はこちらのページ(金融庁公式)にまとめられています。
金融庁は「ICOで発行されるトークンは暗号資産(仮想通貨)である。」と判断しており、暗号資産(仮想通貨)に対して行われる法規制と同様の規制をするとしています。
しかしながら、被害例がまだ少なく周辺法律もあまり整備されていないことから、万が一被害にあった場合に加害者を罪に問える可能性はまだ低いと言えます。
ICOについて詳しくはこちら
仮想通貨の法律 まとめ
暗号資産(仮想通貨)の法律 まとめ
- 暗号資産(仮想通貨)法は、国内の暗号資産(仮想通貨)に関する法律の総称
- 改正資金法には暗号資産(仮想通貨)の定義と暗号資産(仮想通貨)交換業についての定義が定められている
- 暗号資産(仮想通貨)法によって暗号資産(仮想通貨)は金融庁監視のもとでより信頼性がup
- 暗号資産(仮想通貨)についての規制は世界各国で扱いが異なっている
ビットコインなどが生まれた当初は、小さなコミュニティの中で遊びとして使われていたようなものであり、当然課税や規制の対象ではありませんでした。しかし、近年その規模は驚くほど大きくなり、今は世界中にそのネットワークを張り巡らせています。
法定通貨との取引や、決済手段としての浸透を通じて、現実的な価値を持った暗号資産(仮想通貨)は、もはや遊びとはみなされず、マネーロンダリングの危険性もあることから、国の法規制の対象となっています。
法規制されている以上、それを利用する人も「知らなかった」では済まされません。正しい法律を知って、安全に暗号資産(仮想通貨)と関わるようにしましょう。
また、大国の法規制は相場に影響を及ぼします。日本のみならず、他国の法規制に関するニュースも気にするようにすることをオススメします!