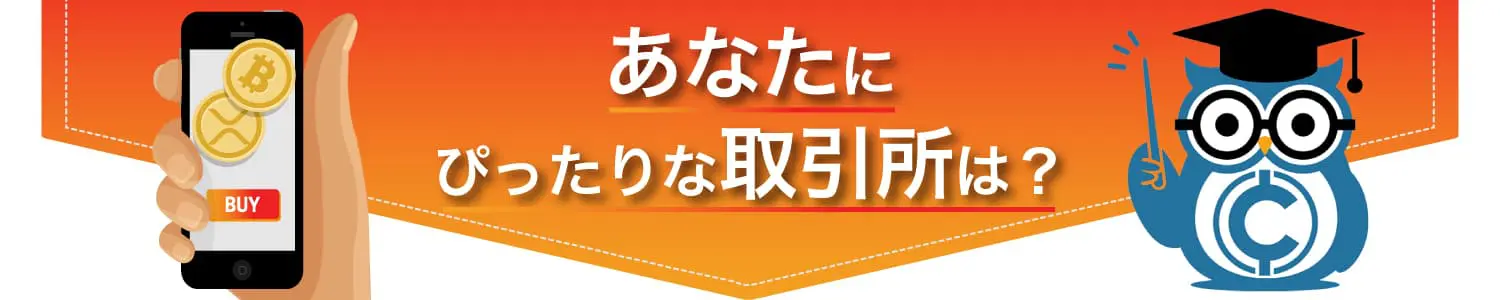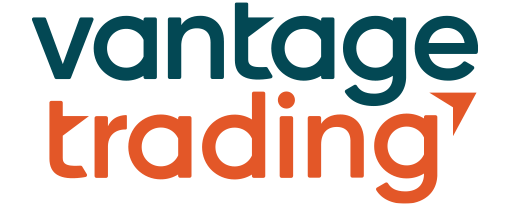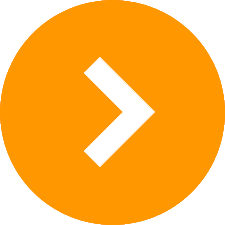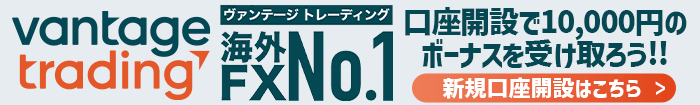ファイナリティとは?ビットコイン決済を理解する上で絶対に欠かせない概念を解説します!

「ファイナリティ」とはもともと決済システムに関連する金融業界の用語でしたが、今ではビットコインやブロックチェーンを理解する上で絶対に理解しておきたい言葉となっています。
この記事を読めば、本来の「ファイナリティ」の意味からビットコインやブロックチェーンにおける意味までしっかり理解することができます。
そもそもファイナリティとは
ファイナリティとは、とても簡単に表現すれば、
「決済が完了した状態」
を指します。
ここでは、より深く「ファイナリティ」について理解して頂きたいので、日本銀行による定義と、実際の決済におけるファイナリティを説明していきます!
日本銀行による説明
「ファイナリティ」は「ファイナリティのある決済」という形で使われることが多いです。その意味は日本銀行のサイトでは「それによって期待通りの金額が確実に手に入るような決済」であると説明されています。
具体的には、以下の2点を満たす決済が「ファイナリティのある決済」であると日銀は述べています。
- 受け取ったお金が後になって紙くずになったり消えてしまったりしない
- 行われた決済が後から絶対に取り消されない
と言われても、なんだかよくわからないですよね。
これから、実際の決済手段におけるファイナリティを説明します!具体例で理解していきましょう!
ファイナリティの具体例
ここでは身近な2つのパターン、すなわち「現金による決済」と「銀行振込による決済」について、どこにファイナリティがあるのか、説明していきます。
現金による決済
まずは現金による決済を考えます。
AさんがBさんに手渡しで10000円支払うとします。
BさんがAさんから10000円札を受け取ります。
Bさんは受け取った10000円札が偽札ではないか確認します。
Bさんの確認をもって、「ファイナリティのある決済」となります。
銀行振込による決済
次に銀行振込による決済を考えます。
今度は、AさんがBさんに手渡しではなく銀行振込で10000円支払うとします。
Aさんの口座残高から10000円が引かれ、Bさんの口座残高が10000円増えます。
まだファイナリティは得られていません。
データ上では決済が完了したように見えますが、もしかしたらAさんの銀行が10000円を持ち逃げしてしまうというリスクがあるからです。
Aさんの銀行からBさんの銀行に10000円の資金が移動し、Bさんの銀行が手元に10000円が届いたことを確認します。
Bさんの銀行の確認をもって、「ファイナリティのある決済」となります。
ここでもう一度「ファイナリティ」の定義に戻ると、
「ファイナリティ」=「決済が完了した状態」
「ファイナリティのある決済」=「それによって期待通りの金額が確実に手に入るような決済」
ですが、わざわざ「確定」や「確実に」と説明されている理由がわかると思います。
「ファイナリティ」という概念をしっかり理解したところで、いよいよブロックチェーン技術におけるファイナリティについても考えていきましょう!
パブリックチェーンとプライベートチェーンのファイナリティを比較!
暗号資産(仮想通貨)のファイナリティはブロックチェーンの型、すなわちパブリック型とプライべート型によって微妙に異なります。
ここでは、2種類のブロックチェーンにおけるファイナリティを比較します!
パブリックチェーン(ビットコイン)のファイナリティは「確率的」!?
パブリックチェーンを使った代表的な暗号資産(仮想通貨)はやはりビットコインです。
ビットコイン決済の場合のファイナリティはどこにあるのでしょうか。
ここでも、具体例を用いて考えてみましょう。
AさんがBさんに1BTCを支払うとします。この取引を以後、「A⇒B」とします。
日本ブロックチェーン協会の定義によれば、ブロックチェーンは「時間の経過とともにその時点の合意が覆る確率が0へ収束するプロトコル」であるとしています。
ビットコインで決済した場合、その取引記録ははブロックチェーン上に記録されていきます。その取引記録が改ざんされてしまうリスクは時間がたつにつれ「確率的」に限りなく0に近づいていきますが、完全に0になることはありません。
ブロックチェーンのファイナリティはコンセンサスアルゴリズムによって異なるのですが、ビットコインが採用するPoW(プルーフ・オブ・ワーク)の場合、「Aさん⇒Bさん」の取引が記録されたブロックに、新たに6個のブロックが承認されてはじめて決済が完了したとみなす場合が多いです。6回のブロック承認の後では決済が覆る可能性が相当低くなるからです。しかしこれは決まりではなく、慣習に過ぎませんから、「厳密にはビットコインにファイナリティはない!」という意見もあります。
また、パブリックブロックチェーンにおいては仮想貨幣の価値が上昇すればマイニング参加者が増え、取引記録を改ざんする(ハッキングする)コストも上がります。そうすれば不正を働くよりも善意のマイナーとして参加した方が得なので、ファイナリティの確率も上がると思われます。
プライベートブロックチェーンのファイナリティは「確定的」!?
現金による決済のファイナリティの説明で「BさんがAさんから受け取った10000円札が偽札でないか確認する」という過程がありました。
実際に日常生活の中で買い物をするときで、お札や貨幣が本物であるかどうかを毎回確認している人は少ないと思います。
また、最近ではビットコイン決済が可能なお店も増えてきました。
つまり、100%のファイナリティを得ていないのに私たちは決済をしていると言えます。
しかし、ビジネスシーンにおいてはファイナリティは重要です。
金融機関での決済システムにブロックチェーンを導入する場合、「確率的なファイナリティ」は受け入れられにくいでしょう。
ビットコインに代表されるパブリックブロックチェーンのファイナリティは「確率的」ですが、プライベートブロックチェーンを用いれば「確定的」なファイナリティを実現できます!
ブロックチェーンの種類について気になる方は以下の2つの記事もチェックしてみてください!
「パブリックブロックチェーンって何?」「プライベートブロックチェーンと何が違うの?」そんな疑問をお持ちの方も少なくないのではないでしょうか?この記事では、2つのブロックチェーンの違いを明らかにした上で、それぞれのメリット・デメリット、活用領域を紹介していきます。暗号資産(仮想通貨)を支えるブロックチェーン技術への理解をより一層深めましょう!目次ひと目でわかるパブリックブロックチェーンとプライベートブロックチェーン!パブリックブロックチェーンとはネットワークの参加者の違い中央管理者の有無による違い承認作業の違い暗号資産(仮想通貨)の違いまとめひと目でわかるパブリックブロックチェーンとプライベートブロックチェーンの違い!パブリックブロックチェーンプライベートブロックチェーンネットワーク参加者自由、不特定多数許可された者だけ中央管理者の有無いないいる承認作業必要必ずしも必要ではない暗号資産(仮想通貨)ビットコイン、イーサリアムなどリップル、企業内通貨などメリット・管理者が必要ない・カウンターパーティーリスクがない・データの改ざんが起こりにくい・価値のある暗号資産(仮想通貨)を作れる・プライバシーが守られている・プロトコルの変更が簡単・マイニング報酬等のインセンティブがいらない・取引承認が早い・取引手数料が安いデメリット・プライバシー情報流出の恐れがある・プロトコルの変更が難しい・取引承認が遅い・取引手数料が高い・管理者によるデータ改ざんのリスクがある・カウンターパーティーリスクがある・不正承認が起こるリスクがあるパブリックブロックチェーンとはそもそもブロックチェーンとはパブリックブロックチェーンについて理解してもらう前に、まずはブロックチェーンについて軽く説明しておきます!ブロックチェーンとは一言で言うと、「トランザクション(取引)を約10分」ごとに区切って1つのブロックとして書き込み、それを前のブロックとチェーン(鎖)のようにつないだもの」です!ブロックチェーンについて厳密に説明すると、とても長くなってしまうのでここでは簡潔に済ませます。もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください! ブロックチェーンの仕組みと理論をわかりやすく説明!初心者向けから上級者向けまで |
確定的なファイナリティを実現しているブロックチェーンのうち代表的なものは以下の3つです。
| プライベートブロックチェーン | 合意形成アルゴリズム |
|---|---|
| Hyperledger Fabric v0.6 | PBFT |
| Hyperledger Fabric v1.0 | PBFTの拡張版 |
| Hyperledger Iroha | PBFTの延長にある「スメラギ」 |
※Hyperledgerとは2015年12月にLinux Foundationによって開始された企業向けのオープンソースのブロックチェーンプラットフォームで、Hyperledger FabricやHyperledger Irohaはそのプロジェクトの一部です。
※PBFTとはPractical Byzantine Fault Toleranceの略称です。ネットワーク上での正しい合意形成を問う「ビザンチン将軍問題」を解決し、P2Pネットワークを正常に稼働させることのできる合意形成アルゴリズムです。
ビザンチン将軍問題についてはコインパートナーのこちらの記事をご覧ください!
不特定多数のノードが参加するパブリックブロックチェーンとは異なり、特定複数のノードが通信して合意形成します。
リーダーノードが一定のタイミングでブロックを生成するので、ブロックが分岐することはなく、合意形成が覆ることはありません。
これがファイナリティが「確定的」である理由です。
マイニングを必要としないので、比較的高速な認証処理が可能だというメリットがあります。
一方で、一般的にノード数が増えるほど合意形成の処理が重くなってしまうというデメリットがあります。
まとめ
繰り返しますが、ファイナリティとは「決済が完了した状態」を意味します。
それがビットコインの場合では「確率的」であり、パブリックブロックチェーン上では「確定的」にすることもできるということです。
パブリックブロックチェーン技術を検討する際は、「確率的な合意形成か、確定的な合意形成かのトレードオフ」を考慮してみるのが一つのポイントになるのではないでしょうか。
ファイナリティを理解することは、金融・経済分野だけでなく、暗号資産(仮想通貨)を理解するために欠かせません!