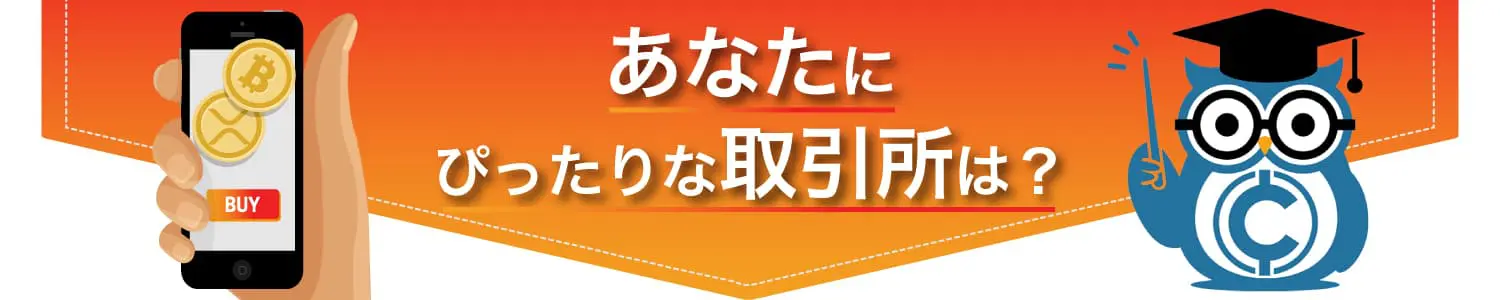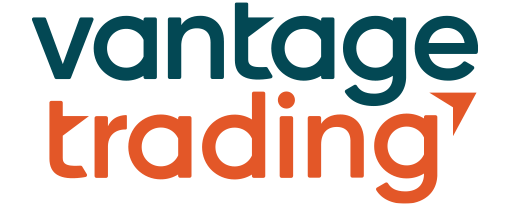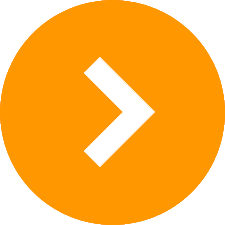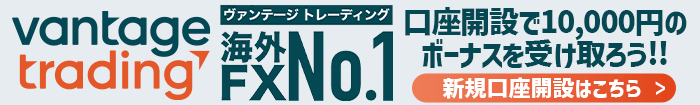パブリックブロックチェーンとは?プライベートブロックチェーンとの違いやメリット・デメリット、ブロックチェーンの未来を解説!

「パブリックブロックチェーンって何?」「プライベートブロックチェーンと何が違うの?」
そんな疑問をお持ちの方も少なくないのではないでしょうか?
この記事では、2つのブロックチェーンの違いを明らかにした上で、それぞれのメリット・デメリット、活用領域を紹介していきます。
暗号資産(仮想通貨)を支えるブロックチェーン技術への理解をより一層深めましょう!
目次
ひと目でわかるパブリックブロックチェーンとプライベートブロックチェーンの違い!
| | パブリックブロックチェーン | プライベートブロックチェーン |
| ネットワーク参加者 | 自由、不特定多数 | 許可された者だけ |
| 中央管理者の有無 | いない | いる |
| 承認作業 | 必要 | 必ずしも必要ではない |
| 暗号資産(仮想通貨) | ビットコイン、イーサリアムなど | リップル、企業内通貨など |
| メリット | ・管理者が必要ない ・カウンターパーティーリスクがない ・データの改ざんが起こりにくい ・価値のある暗号資産(仮想通貨)を作れる |
・プライバシーが守られている ・プロトコルの変更が簡単 ・マイニング報酬等のインセンティブがいらない ・取引承認が早い ・取引手数料が安い |
| デメリット | ・プライバシー情報流出の恐れがある ・プロトコルの変更が難しい ・取引承認が遅い ・取引手数料が高い |
・管理者によるデータ改ざんのリスクがある ・カウンターパーティーリスクがある ・不正承認が起こるリスクがある |
パブリックブロックチェーンとは
そもそもブロックチェーンとは
パブリックブロックチェーンについて理解してもらう前に、まずはブロックチェーンについて軽く説明しておきます!
ブロックチェーンとは一言で言うと、
「トランザクション(取引)を約10分」ごとに区切って1つのブロックとして書き込み、それを前のブロックとチェーン(鎖)のようにつないだもの」
です!
ブロックチェーンについて厳密に説明すると、とても長くなってしまうのでここでは簡潔に済ませます。
ブロックチェーンはパブリックブロックチェーンとプライベートブロックチェーンというように2種類に分けることができます。
では、それぞれ説明していきます!
パブリックブロックチェーンとプライベートブロックチェーン
パブリックブロックチェーンとプライベートブロックチェーンの最大の違いは何でしょうか。
それは、「誰が取引の承認を担っているのか」という点にあります。
「誰でも、自由に」承認できるのがパブリックブロックチェーン(オープン型とも言われます)
「許可された者だけが」承認できるのがプライベートブロックチェーン(許可型とも言われます)
です。
4つの違い
パブリックブロックチェーンとプライベートブロックチェーンの4つの違い
- ネットワーク参加者の違い
- 中央管理者の有無による違い
- 承認作業の違い
- 暗号資産(仮想通貨)の違い
パブリックブロックチェーンとプライベートブロックチェーンを分ける大きな違いとして、「誰が取引の承認を担っているのか」という点を挙げました。
それは言い換えれば、「ネットワークの参加者の違い」ということになります。
ところで、上ではプライベートブロックチェーンを「許可された者だけが取引を承認できるブロックチェーン」として説明しましたが、ここで「許可」とは誰が与えるものなのでしょうか。
それは「中央管理者」です。
「え!ブロックチェーンは非中央集権という理念のもとに作られた技術だから、中央管理者なんで存在しないでしょ!」と思う方が多いかと思います。
ですが、プライベートブロックチェーンには中央管理者が存在します。(中央管理者が複数存在するブロックチェーンはコンソーシアムブロックチェーンと呼ばれます。)
ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)を支えるブロックチェーンは「非中央集権(=中央管理者がいない)」のもとで成り立つパブリックブロックチェーンです。
それに対して、「中央管理が適した領域にもブロックチェーン技術を応用したい」というニーズを満たすのがプライベートブロックチェーンです。
以上より、「中央管理者の有無による違い」も2つのブロックチェーンを分ける大きな違いとなります。
また、取引の承認に関して、2種類のブロックチェーンの間では「誰が承認するのか」も違いますが「どのように承認するのか」も違います。
そして、それぞれのブロックチェーンを使ってどのような暗号資産(仮想通貨)が生まれるのかも違います。
これから、4つの違いについてそれぞれ詳しくみていきましょう。
2種類のブロックチェーンの違いを理解すれば、それぞれのメリット・デメリットや活用領域が見えてきます!
ネットワークの参加者の違い
誰でも参加できるパブリックブロックチェーン
パブリックブロックチェーンでは取引記録等の情報が参加者全員で分散管理されています。
言い換えれば、世界中誰でも取引記録を閲覧可能だということです。
この管理方法をプライバシーの観点からみると、「プライバシーが守られていない」というデメリットになってしまいます。
許可された者しか参加できないプライベートブロックチェーン
一方、プライベートブロックチェーンでは、取引記録等の情報は、中央管理者に許可された一部の者だけで管理されています。
プライベートブロックチェーンの名前からもわかるように、「プライベート」なので、「プライバシーが守られている」といえます。
一般企業がプロジェクトでブロックチェーンを運用する場合では、顧客情報を外部へ流出しないように管理する必要があります。
そのときに、「プライバシーが守られている」という点は大きなメリットとなります。
中央管理者の有無による違い
管理者がいないパブリックブロックチェーン
メリットとして、「カウンターパーティーリスクがない」という点が挙げられます。
カウンターパーティーリスクとは中央機関の情報漏洩や改ざんによって被害を受けることを指します。
中央管理者が存在しないパブリックブロックチェーンではカウンターパーティーリスクの心配がありません。
また、デメリットとして「プロトコルの変更が難しい」という点が挙げられます。
独裁的にプロトコルが変更されてしまう危険を防ぐためにはメリットですが、素早い仕様の変更を必要とするシステムにおいてはデメリットとなります。
ですので、開発当初のプロトコルのクオリティが非常に重要です。
管理者が存在するプライベートブロックチェーン
メリットとして「プロトコルの変更が簡単」という点が挙げられます。
システムに欠陥が見つかって改善したいときなど、中央管理者が素早く簡単にプロトコルに手を加えることができます。
「プロトコルの変更が簡単」ということは、裏を返せば「管理者によるデータ改ざんの恐れがある」というデメリットになってしまいます。
管理者がデータを改ざんすれば、「カウンターパーティリスク」にもつながります。
承認作業の違い
承認が「遅い・高い」パブリックブロックチェーン
「中央管理者が存在せず」「誰でも自由に参加できる」パブリックブロックチェーン上で、改ざんや二重承認が起こらないように、非常に厳密な承認アルゴリズムが採用されています。
例えば、ビットコインではPoW(プルーフ・オブ・ワーク)というコンセンサスアルゴリズムが用いられています。
パブリックブロックチェーンにおいて「改ざんが起こりにくい」という点はメリットです。
しかしそのような厳密さゆえ、「取引の承認に時間がかかってしまう」というデメリットが生じます。
ビットコインの取引の場合、約10分かかってしまいます。
また、「取引にかかる手数料が高い」というデメリットも挙げられます。
PoW(プルーフ・オブ・ワーク)について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
目次プルーフオブワークとはプルーフオブワークとマイニングの仕組みプルーフオブワークとプルーフオブステークの違い承認システムは他にもある! プルーフオブワークまとめ プルーフオブワークとは プルーフオブワーク(Proof of Work)とは、ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)で採用されている、膨大な計算量を必要とする作業を成功させた人が取引の承認者となり、新たなブロックをブロックチェーンに繋ぐ権利を得られる仕組みのことです。その計算作業をマイニングと言い、マイニングの成功者には報酬が与えられます。 膨大な計算力が必要な作業って?マイニングって?と思った方、これからその説明をしていくので安心してください! プルーフオブワークとマイニングの仕組み ハッシュ関数が重要! プルーフオブワークの説明に入る前に、まずはハッシュ関数というものを説明しなければなりません。このハッシュ関数というのは、値を代入して計算するのは簡単なのに、この値が出るにはどういう値を代入すればいいかが分からないという特殊な関数です。この特徴を活かしてプルーフオブワークという仕組みは成り立っています。 マイニングとはどんな作業? プルーフオブワークにおいて、取引を承認し新しいブロックをブロックチェーンに繋げる作業のことをマイニングといいます。このマイニングを最初に成功させた人は報酬がもらえるという仕組みになっています。では、どうやって新しいブロックを繋げる人を決めるのでしょうか。 マイニングという作業において実際にやっていることは、ハッシュ関数に代入するとその頭に決められた個数の0が並ぶ数字が出てくるような値(ナンス)を探すという作業です。つまり、マイニングの成功とはナンス探しの成功を指します。 さて、ここでさっきのハッシュ関数の性質を思い出してください。ハッシュ関数は代入して計算をするのは簡単だけど、その逆を求めるのは困難です。すなわち、「値を代入したときに頭に0が何個並ぶか」はすぐ分かるのに、「頭に0がこの個数並ぶ数が出てくるには何の値を代入すればいいか」は分からないわけです。
承認が「早い・安い」プライベートブロックチェーン
プライベートブロックチェーンでは、中央管理者に許可された者だけがネットワークに参加することができ、それらの参加者の間で取引承認が行われます。
パブリックブロックチェーンにおける不特定多数による承認スピードとプライベートブロックチェーンにおける特定少数による承認スピードを比べたら、プライベートブロックチェーンの承認の方が早いというのは簡単にイメージできると思います。
つまり、プライベートブロックチェーンには、「取引の承認が早い」「取引にかかる手数料が安い」というメリットがあります。
承認が「早い・安い」といったメリットの反面、「不正承認が起こるリスクがある」というデメリットも生まれてしまいます。
仮想通貨の違い
大半の暗号資産(仮想通貨)がパブリックブロックチェーンを採用している
パブリックブロックチェーンは最初に登場したブロックチェーンです。
いくつかあるブロックチェーンの原型となる種類であり、その他のものはパブリックブロックチェーンから派生したものです。
パブリックブロックチェーンでは価値のある暗号資産(仮想通貨)を作ることができます。
なぜなら、誰もがそのネットワークに参加することができ、ブロック承認の検閲性や透明性が高いからです。
実際、ビットコイン、イーサリアムなどの主要通貨は全てパブリックブロックチェーンによって運営されています。
またICOで発行されるトークンのほとんどは、ERC20というイーサリアムの規格に則っており、パブリックブロックチェーン上に存在しています。
ERC20について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください!
2018年、コインパートナーが最もおすすめする暗号資産(仮想通貨)はこちら!! 目次ERC20とは?トークンにも違いがある?ERC20に対応するおすすめウォレット!ERC20準拠の token list(トークン一覧表)!ERC20 まとめ ERC20とは? 暗号資産(仮想通貨)への投資をして、または投資に興味があって情報収集をしている際に、ICOに興味を持った方も多いのではないでしょうか。「ICO参加して爆益出したわww」など、超ハイリスク・ハイリターンな投資ですが、ICOについて調べる中で、「ERC20ってなに?」と疑問に思った方のために、コインパートナーが徹底解説します!※2018年4月26日現在、ERC20にトークンが無限生成できるバグが見つかり、多くの取引所でERC20トークンの入金を停止しています。 ERC20って暗号資産(仮想通貨)なの? 結論から言うと、ERC20は暗号資産(仮想通貨)ではありません。ERC20は特定の暗号資産(仮想通貨)の名前ではないので、「ERC20の相場の動きが~」や、「ERC20~枚買った」などといった使い方はしない、ということですね! ICO(initial coin offering)とは、資金調達をしたいスタートアップが新たな暗号資産(仮想通貨)(トークン)を発行・販売して資金調達をする方法のこと (下記事より抜粋)ですが、その発行されたトークンが、スタートアップごとに全く異なる仕組み(プログラミング言語など)をしていると、受け取る側がそれぞれに対応することになり大変なので、「みんなでルールを統一しよう」となってできた、トークンに対する技術的な統一された仕様(についての議論)がERC20(Ethereum Request for Comments: Token Standard #20) になります。 バラバラに作ると受け手が混乱する ICOとは?暗号資産(仮想通貨)を用いた新たな集金方法!参加方法やおすすめ案件を解説!今世界で大注目の新しい資金調達の方法であるICOですが、実際にどうやって行うのか、またどうやって参加するのか、メリットやリスクはなんなのか、わからない方も多いかと思います。そんなICOについて解説してみました。続きを読む ICOについて詳しく知りたい方はこちら!
プライベートブロックチェーン
プライベートブロックチェーンでは参加者が制限されているので、そのネットワーク内で有効な暗号資産(仮想通貨)(トークン)しか作ることができません。
金融機関や一般企業などによる利用が想定されています。
リップルが有名です。
まとめ
ひと目でわかるパブリックブロックチェーンとプライベートブロックチェーンの違い!
| | パブリックブロックチェーン | プライベートブロックチェーン |
| ネットワーク参加者 | 自由、不特定多数 | 許可された者だけ |
| 中央管理者の有無 | いない | いる |
| 承認作業 | 必要 | 必ずしも必要ではない |
| 暗号資産(仮想通貨) | ビットコイン、イーサリアムなど | リップル、企業内通貨など |
| メリット | ・管理者が必要ない ・カウンターパーティーリスクがない ・データの改ざんが起こりにくい ・価値のある暗号資産(仮想通貨)を作れる |
・プライバシーが守られている ・プロトコルの変更が簡単 ・マイニング報酬等のインセンティブがいらない ・取引承認が早い ・取引手数料が安い |
| デメリット | ・プライバシー情報流出の恐れがある ・プロトコルの変更が難しい ・取引承認が遅い ・取引手数料が高い |
・管理者によるデータ改ざんのリスクがある ・カウンターパーティーリスクがある ・不正承認が起こるリスクがある |
いかがでしたでしょうか?
パブリックブロックチェーンとプライベートブロックチェーンの間には大きく分けて4種類の違いがあり、それらの特徴がメリットにもデメリットにもなります。
パブリックブロックチェーンはブロックチェーンの元祖です。プライベートに運用する場合でも、パブリック型の特徴やメリット・デメリットを把握しておく必要があります。
パブリックブロックチェーンは「完全に自立分散的で、中央集権的な既存の枠組みとは根本的に相容れないモデル」であり、
プライベートブロックチェーンは「中央管理に適した、既存の枠組みを大きく変えずに効率化を進めるモデル」と言えます。
それぞれのブロックチェーンのベクトルは大きく異なっているので、優劣の関係はなく、それぞれの活用領域を見極めることが重要です。
インターネットが影響を与えなかった分野がないのと同様に、ブロックチェーンは情報と記録が関係する全ての分野に影響を与えることができます。
金融系ではもちろん、資金調達や商品流通管理分野など、活用される領域は多岐にわたるでしょう。
今後も、ブロックチェーン技術の発展から目が離せませんね!