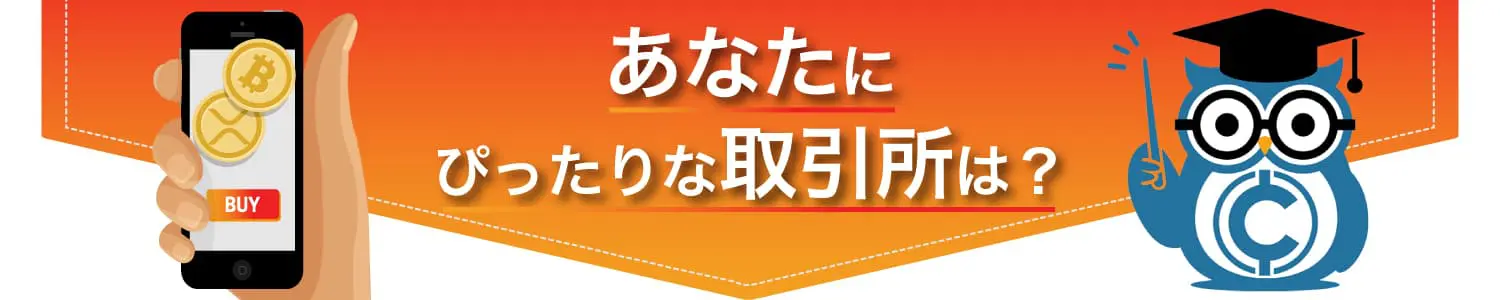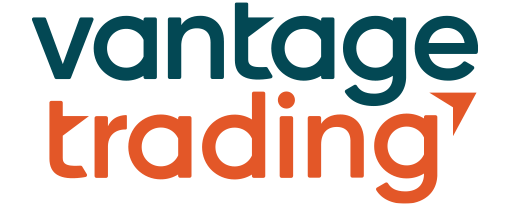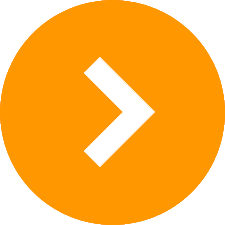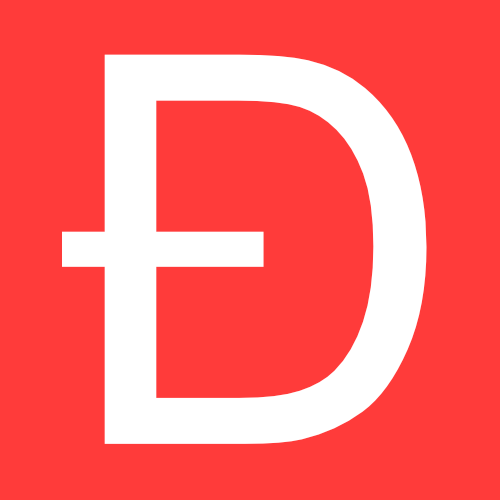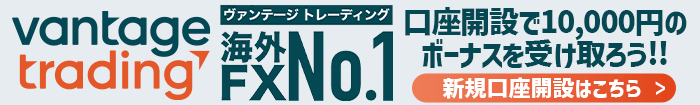ブロックチェーンの分岐(フォーク)とは?目的や仕組み、ハードフォーク・ソフトフォークの特徴などを徹底解説!
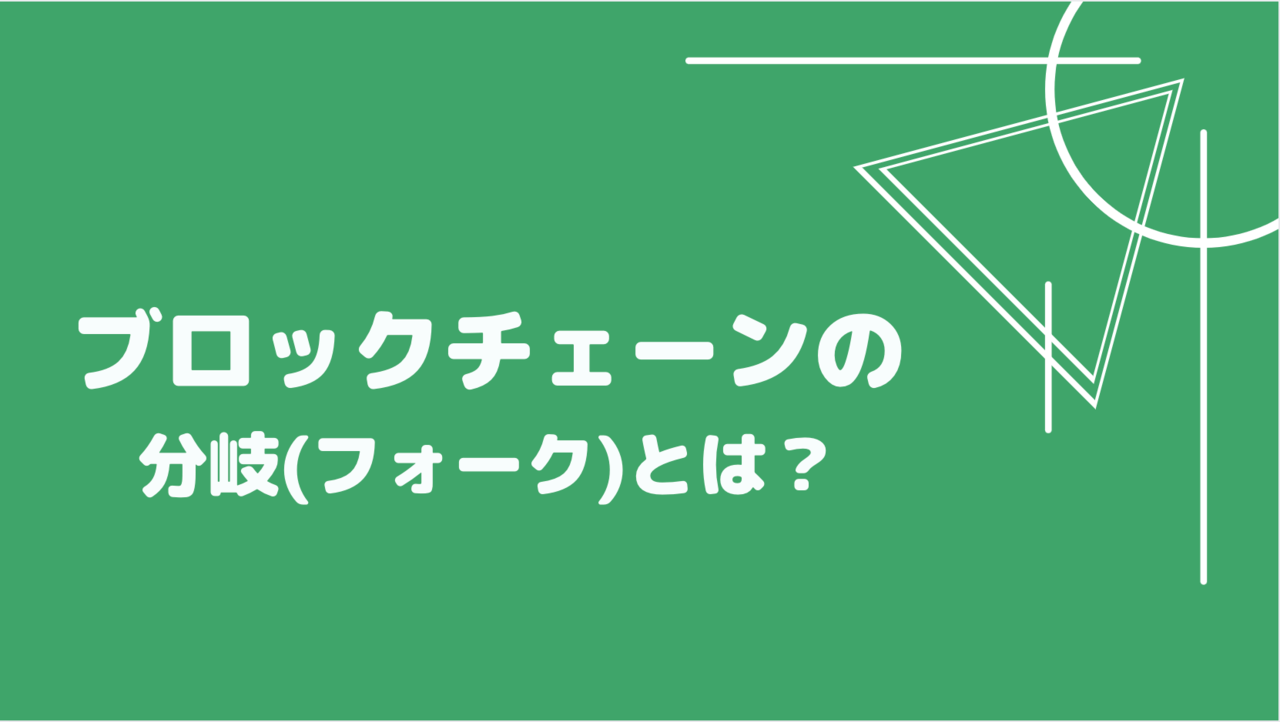
「ブロックチェーンの分岐(フォーク)って何?」
そう考えている方も多いかと思います。
そこで今回この記事では、ブロックチェーンの分岐(フォーク)がどのようなもので、何が原因で起きているのか、またフォークの種類やそれぞれの特徴について解説しています。
この記事を読み終わる頃には、ブロックチェーンの分岐(フォーク)について理解し、自分の保有する通貨に分岐が起きても十分に対応できるようになるでしょう!
この記事の内容をざっくりまとめると•••
- 分岐とはブロックチェーンが2つの枝に分かれること
- 基本的に分岐は最終的に1つの枝に収束する
- 分岐には、偶発的なもの・悪意のあるもの・計画的なものがある
- ハードフォークとソフトフォークはブロックチェーンの性能をよくすることができる
- ハードフォークでは新しい通貨が誕生する
目次を開く
ブロックチェーンの分岐(フォーク)とは

ブロックチェーンの分岐(フォーク)とは、同時に複数のブロックがマイニングされたことなどによって、同じブロックの後に複数のブロックが加えられた際に発生します。
この時ブロックチェーンは分岐し、次のブロックを作成するマイナーは分岐したチェーンの中から、1つの枝を選び、そこに自分のブロックを加えるように計算を行います。
このようにして分岐した枝には徐々に長さに差が生まれ、その差が一定以上になると、短い方の枝は捨てられ、短い方のブロックをマイニングした人はマイニング報酬を受け取ることができなくなります。
このインセンティブ設計により、基本的にブロックチェーンは仮に分岐が起きてもマイナーが1つの長い枝に集中するようになり、最終的に1つの枝に収束するようになっています。
ブロックチェーンの分岐(フォーク)が起きるパターン

ブロックチェーンの分岐は、大きく分けて3つのパターンで起きます。
ブロックチェーンの分岐(フォーク)が起きるパターン
- 偶発的なもの
- 悪意のあるもの(51%攻撃)
- 計画的なもの(ハードフォーク・ソフトフォーク)
偶発的なもの

ブロックチェーンの分岐は、2人以上のマイナーがマイニングをほぼ同時に成功させた時に起こります。
そもそもマイニングとは、マイナーがナンスという特別な値(1通りとは限らない)を探す作業のことです。
そのナンスを発見した人はマイニング成功となり、その結果をネットワークに流すことで、次のブロックを生成することが出来ます。
ですが、ほぼ同時に2人以上の人が別のナンスを見つけ、ネットワークに流せば2人以上の人がマイニング成功になります。
その時、2人は別のブロックを生成しブロックチェーンにつなげるので、ブロックチェーンの分岐が起きます。
悪意があるもの(51%攻撃)

上記の偶発的な分岐は起きる確率が通常0.2%ほどですが、それを意図的に悪意をもって起こすことができます。
簡単に説明すると、マイニングのハッシュレートの51%以上を1人で持つことで、取引の承認権を独占するというもので、51%攻撃と呼ばれています。
この51%攻撃が成立すると、
- マイニング報酬の独占
- 正当な取引のキャンセル
- 取引の二重支払い
などが簡単にできるようになってしまいます。
ただ、過半数のハッシュレートを持つこと自体があまり現実的でないほど難しいことなので、51%攻撃が起こることはほとんどありません。
また、51%攻撃ができたとしてもその通貨の信頼性が低下し、価格が暴落してしまうことが予想されるため、51%攻撃を行うインセンティブがあまりありません。
計画的なもの(ハードフォーク・ソフトフォーク)

ブロックチェーンの分岐には、仮想通貨をより良いものに改善するため、計画的に行われるものがあります。
例えば、仮想通貨は利用者の増加によって処理速度が遅くなってしまうスケーラビリティ問題を抱えていますが、計画的な分岐により、処理速度が数倍速くなるようなアップデートが行われたりします。
その他にも、ハッキング事件の事後処理などが目的で行われます。
このような計画的な分岐には、「ソフトフォーク」と「ハードフォーク」の2種類あり、それぞれ分岐の仕方が大きく異なります。
ハードフォークとソフトフォークの違い

ハードフォークの仕組み

ハードフォークでは、ブロックチェーン自体の仕様変更を行い、旧仕様と新仕様のブロックの互換性がなくなるため、ブロックチェーンは永続的に分岐します。
そのため新仕様のブロックが生成されても旧仕様のブロックは機能的にそのまま使用することができます。
これにより、本来は仕様を変更するために行われるハードフォークですが、結果的に旧仕様の通貨に加え、新仕様の新しい通貨が誕生します。
ソフトフォークの仕組み

ソフトフォークでは、旧仕様と新仕様の互換性を保ったまま仮想通貨自体の仕様変更を行うため、ハードフォークのような通貨の分裂は起きません。
主にユーザビリティの向上を目的として行われます。
一時的な分岐はありますが、新しい仕様が安全に稼働することが確認されると新仕様の枝に収束していきます。
またハードフォークと異なり、変更前に生成された過去のブロックも対象に仕様変更を行います。
ハードフォークのメリット

ハードフォークのメリット
- ブロックチェーンの機能が向上する
- 自動的に通貨が貰える
- 通貨の価格が上昇する
ブロックチェーンの性能が向上する

ハードフォークでは、スケーラビリティ問題などを解決するために行われることがあります。
そのため、ハードフォーク以前と比較してブロックチェーンの性能が向上し、より実用的で使いやすい通貨が誕生します。
さらに、これまでになかった新しい機能が付け加えられることもあります。
自動的に通貨が貰える

ハードフォークでは、通貨が2つに分裂すると説明しましたが、旧仕様の通貨を保有していると、同量の新仕様の通貨を付与されることがあります。
例えば、ビットコインを10BTC保有している状態でビットコインのハードフォークが行われ、新規通貨が発行されたとすると新しい通貨が10枚付与されます。
受け取った通貨が将来的に大きな価値を持つと、その分ただで利益を得られる可能性があります。
実際にビットコインから分裂したビットコインキャッシュや、イーサリアムから分裂したイーサリアムクラシックは、多くの仮想通貨取引所に上場し、高い価格を付けています。
ただ、ハードフォークによって新しい通貨が付与されるのかどうかは仮想通貨取引所の方針によって異なるため、新規通貨の付与を発表している仮想通貨取引所にハードフォーク前に通貨を預けておく必要があります。
通貨の価格が上昇する

ハードフォークによって通貨の性能が向上すると、通貨としての需要が高まり、価格が高騰することがあります。
特にハードフォーク前には、分裂後の新通貨付与の期待も相まって、価格が上昇する傾向にあります。
ただハードフォーク後に関しては、アップデートの内容によっては急落する可能性も考えられるため、慎重な判断が必要になります。
取引初心者の方はハードフォーク前後での取引を控えるのが無難でしょう。
ハードフォークのデメリット

ハードフォークのデメリット
- 通貨が失われる可能性
- コミュニティが分裂する可能性
- 信頼感が失われる可能性
通貨が失われる可能性

ハードフォークでは互換性のない、新しいブロックチェーンが誕生します。
そのため、ハードフォーク中にその通貨を送金すると、エラーが発生し、通貨が送金先に着金せず、失われる可能性があります。
取引所によってはハードフォーク中の通貨の取引や送金を一時的に停止するなどの対応をとりますが、そうでない場合は注意が必要です。
ある程度の混乱が起こるため、ハードフォーク中や直前直後は取引や送金は控えるようにしましょう。
コミュニティが分裂する可能性

ハードフォークは通貨のアップデートとしては大規模で、通貨の保有者などに大きな影響を与えます。
そのため、その通貨のコミュニティ内で、ハードフォーク後にどちらの通貨のコミュニティに属するか意見が分かれることがしばしば見受けられます。
仮想通貨の中には、熱烈なコミュニティによって価格が支えられている場合もあるため、コミュニティの分裂によって価格が急落する可能性も考えられます。
信頼感が失われる可能性

通貨になんらかの不具合が生じた際や大規模なハッキングがあった際に、毎回ハードフォークを行うと、通貨としての信頼感が薄くなってしまいます。
そもそも暗号資産(仮想通貨)は、発行数があらかじめ決まっており、それによって希少性が生まれ、金融商品として成り立っています。
しかし、ハードフォークによって新しい通貨ができてしまうと、その希少性がなくなってしまうという懸念があります。
ハードフォークの実例

ハードフォークの実例
- ビットコインとビットコインキャッシュ
- イーサリアムとイーサリアムクラシック
- ビットコインキャッシュとビットコインキャッシュSV
ビットコインとビットコインキャッシュ

2017年8月1日にビットコインのハードフォークが行われ、ビットコインとビットコインキャッシュに分裂しました。
分裂の原因は、ビットコインが直面していたスケーラビリティ問題の解決策に対する意見の対立でした。
「取引記録データの容量を減らす」と「1ブロックあたりに入れられるデータの量を増やす」という2つの案がありました。
前者はソフトフォークで一つの取引記録のデータを元の約60%に縮小できる「SegWit」を導入しようと考えました。
しかし、SegWitはマイニングアルゴリズム「ASICBoost」に対応してないため、マイナーから反対されました。
マイナーは、後者の「1ブロックあたりに入れられるデータ量を8倍に増やす」方法を主張しました。
そこで妥協案として、一旦SegWitを導入して、その後1ブロックあたりの容量を2倍にする「SegWit2x」が採用されることになりました。
しかし、SegWit2xもASICBoostが使えないため、マイナーからの反対意見が強く出たままでした。
そこで2017年8月1日に1ブロックあたりの容量を8MBまで拡大するハードフォークが行われ、ビットコインキャッシュが誕生しました。
イーサリアムとイーサリアムクラシック

2016年7月20日にイーサリアムのハードフォークが行われ、イーサリアムとイーサリアムクラシックに分裂しました。
分裂の原因は、イーサリアムのブロックチェーン上に書かれたThe DAOのスマートコントラクトに致命的なバグがあったことによるものです。
The DAOとは、イーサリアムのスマートコントラクトを使用して作られた非中央集権の分散型投資ファンドのICOプロジェクトです。
致命的なバグを攻撃され、DAO内の全資産の約3分の1(当時のレートで8000万ドル)が盗まれてしまいました。
その対応策として、イーサリアムはソフトフォークした後に、ハードフォークしました。
ソフトフォークでは、盗まれたイーサリアムが使用できなくなるように仕様変更しました。
これにより、大規模なハッキングをしようとするインセンティブを減らすことができます。
また、この件の犯人がイーサリアムの市場に対して大きな影響力を持つことを防ぎました。
ハードフォークでは、盗まれた時の履歴を消去して盗まれた資産を盗まれた元のところに戻す作業が行われました。
そして、ハードフォーク後に新たに出来たブロックチェーンがイーサリアムの正式なチェーンになりました。
しかし、一連の対応があまりにも中央集権的だったことから、一部から強い反感を受けました。
その結果、旧ブロックチェーンがイーサリアムクラシックとして、その人達から支持を受け、今も残っています。
ビットコインキャッシュとビットコインキャッシュSV

2018年11月16日ビットコインキャッシュのハードフォークが行われ、ビットコインキャッシュとビットコインSVに分裂しました。
分裂の原因は、ビットコインキャッシュの開発者であるBitcoin ABCとBitcoin SVの対立です。
Bitcoin ABCは、以下の2点をアップデートに盛り込もうと考えました。
- 外部の情報をブロックチェーンに取り込むオラクルを活用したスマートコントラクトの実装
- 異なるブロックチェーン上のトークンを取引所の仲介なしに直接取引できるクロスチェーンの実装
Bitcoin SVは、以下の2点をアップデートに盛り込もうと考えました。
- ブロック容量を32MBから128MBに拡張する
- 以前排除されたビットコインのコードを復活させ、スクリプトを増やす
結果的にハードフォーク後、Bitcoin ABC側がビットコインキャッシュ、Bitcoin SV側が新しい暗号資産(仮想通貨)のビットコインSVに採用されました。
ソフトフォークのメリット

ソフトフォークのメリット
- ハードフォークよりも混乱が少ない
- セキュリティや取引速度が高まる
- 性能が向上し、価格上昇につながることが多い
ハードフォークよりも混乱が少ない

ハードフォークでは、チェーンが分裂し新しい暗号資産(仮想通貨)が誕生するため、それに伴う混乱が少なからず発生してしまいます。
一方で、ソフトフォークは一時的に分岐はおきますが、やがて1つのチェーンに収束します。
ソフトフォークは暗号資産(仮想通貨)の利用者の混乱が少なく、その上で性能を向上させることが可能です。
セキュリティや取引速度が高まる

ソフトフォークは通貨の性能を向上させるものですが、具体的にはセキュリティや取引速度を向上させる場合が多いです。
ハードフォークと比べると改善の幅には限界がありますが、その分、互換性を保ったまま性能を引き上げることが可能となっています。
性能が向上し、価格上昇につながることが多い

ソフトフォークでは、暗号資産(仮想通貨)のセキュリティや取引速度が改善されるため、ソフトフォーク後の通貨は需要が高まる傾向にあります。
暗号資産(仮想通貨)に詳しいトレーダーなら、ソフトフォークによる価格上昇を狙って投資することは基本でしょう。
ただし現状としては、暗号資産(仮想通貨)は投機対象としての見方が強いため、ソフトフォーク後は売り圧力が高まりやすいという傾向があります。
ソフトフォークのデメリット

ソフトフォークのデメリット
- 仕様変更による混乱
- バグが発生する可能性
仕様変更による混乱

先ほど、ソフトフォークはハードフォークよりも混乱が少ないことをメリットとして挙げましたが、ソフトフォークによる混乱も全く起こらないわけではありません。
もし、自分の所持していた暗号資産(仮想通貨)でソフトフォークが行われた際には、何がどのように変更されたのかを十分に知っておく必要があるでしょう。
その上で、一度売却するのか保持しておくのかを判断しましょう。
バグが発生する可能性

暗号資産(仮想通貨)は特定の管理者が存在しない「非中央集権」的なシステムとして有名ですが、ソフトフォークは自動で行われるものではなく、あくまでも人間が実行するものです。
そのため、ソフトフォーク後に思わぬバグが発生してしまう可能性があります。
最悪の場合、暗号資産(仮想通貨)そのものが消失してしまう可能性もゼロではないため、ソフトフォーク直後は取引するのをなるべく避けた方が良いでしょう。
ソフトフォークの実例

ビットコインのP2SH(Pay to Script Hash)

ビットコインには、2014年4月1日にP2SH(Pay to Script Hash)というものがソフトフォークによって導入されました。
P2SHというのは、ビットコインを受け取りたい人があらかじめ専用のアドレスを生成し、それを自らが指定した送る人に渡して取引をするシステムのことで、マルチシグのための1つの方法です。
これによってセキュリティを格段に強化するとともに、送金する側の負担する手数料を抑えることができるようになりました。
SegWit(セグウィット)

Segwitは取引データを圧縮することで、一つのブロックに記録できるデータを増やす仕組みのことです。
あくまでも、1つのブロックに含むデータの量を調整しているため、ブロックのサイズが拡大しているサイズが拡大している訳ではありません。
Segwitはその有用性から、ビットコインやモナコイン、ライトコインなどの様々な暗号資産(仮想通貨)でソフトフォークによって導入されています。
ブロックチェーンの分岐に関するQ&A

計画的なフォークがあるときはどのように対応すればいいの?
ハードフォーク、ソフトフォークにかかわらず、フォーク中やその前後での通貨の送金や取引はできる限り控えることをおすすめします。
また、そのフォークの内容が通貨に良い影響を与えるのかどうかを慎重に判断し、フォーク時に通貨を保有しておくのかどうかを決めておきましょう。
特に価格が変化しやすいタイミングなので、取引に慣れていない初心者の方は大人しく静観した方が良いでしょう。
ハードフォークで生まれる新しい通貨はどうやって受け取るの?
ハードフォークによって新しく誕生する通貨が受け取れるかどうか、またどのようにして受け取るのかは取引所によって異なります。
そのため取引所のホームページやTwitterアカウントから詳細を確認するようにしましょう。
ブロックチェーンの分岐(フォーク) まとめ
ブロックチェーンの分岐(フォーク) まとめ
- 分岐とはブロックチェーンの枝が2つに分かれること
- 基本的に分岐は最終的に1つの枝に収束する
- 分岐には偶発的なもの、悪意があるもの、計画的なものがある
- ハードフォークはブロックチェーン自体の仕様変更で、新しい通貨が誕生する
- ソフトフォークは仮想通貨自体の仕様変更で、分岐はいずれ収束する
この記事では、ブロックチェーンの分岐について、発生する理由や目的、ハードフォーク・ソフトフォークそれぞれの特徴などについて詳しく解説しました。
ブロックチェーンの分岐、特にハードフォーク・ソフトフォークは、仮想通貨自体の価格にも大きな影響を与えるため、取引している方は常にチェックしておきましょう!
また、ハードフォーク時は分裂後の通貨を受け取ることができるのかは取引所によるため、利用している取引所のお知らせやTwitterアカウントを確認するようにしましょう!