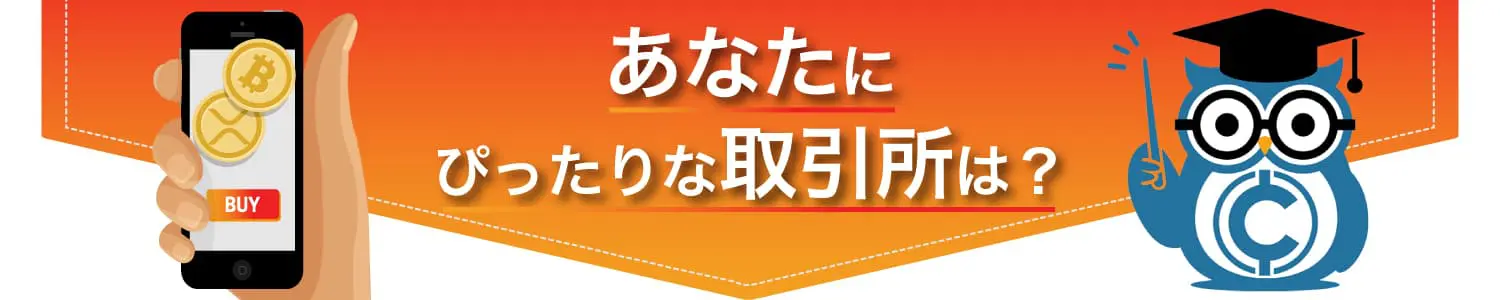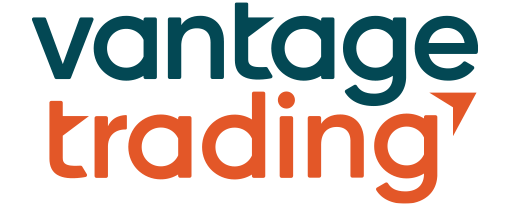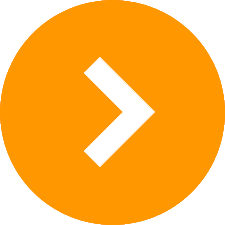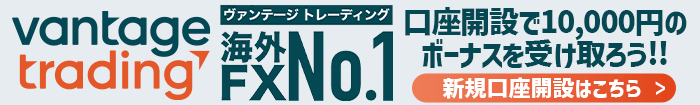リップルのILPとは?世界の価値を繋げる技術の概要・仕組みを徹底解説!

「ILPって何?」「リップルと関係あるの?」
そう思っている方も多いのではないでしょうか。
ILPとは"Interledger Protocol"(インターレジャープロトコル)の略称です。
”Interledger Protocol”を直訳すると「台帳間の規格」となりますが、これではILPのスゴさが全くわかりませんね。
この記事ではILPという未来の世界を変える可能性を持つ技術について、詳しく解説していきます!
ILPとは
ILP(インターレジャープロトコル)とは一言でいうと、「異なる台帳間で価値の移動を行うための規格」です。
例えば、ビットコインと現金を交換する場合を考えます。
ビットコインが記録されているブロックチェーンと、日本円が記録されている銀行口座システムはそれぞれ規格が異なります。ここで、2つの台帳の間にILPが仲介として入り込むことで、異なる台帳同士でもスムーズに価値の移動ができるようになるということです。
このILPという技術は、Ripple Productのうちの一つであるxCurrentにも応用されています。
ILPは2015年10月にリップル社が提唱しました。リップル社の目指すIoV (Internet of Value )の実現には必要不可欠な技術です。現在は、W3Cによって標準化が進められています。
W3Cとは”World Wide Web Consortium”の略称で、Web技術の標準化を行う非営利団体です。
まとめると、ILPは、あらゆる価値をシステム上で簡単に移転できるようにするための決まりごとであり、世界中のWeb技術に影響力のあるW3Cによって開発されています。
ILPが想定している4つの接続先
ここではILPが想定している4つの接続先を紹介していきます。
ブロックチェーンネットワーク
ビットコインやイーサリアムなどのブロックチェーンです。
これらのブロックチェーンがILPによって接続されると、BTCとETHの交換が非常にスムーズになります。
いま、BTCとETHを交換する場合、
ビットコインブロックチェーン→取引所→ライトコインのブロックチェーン
というように一回取引所を経由しなければなりません。なぜなら、2つのブロックチェーンの規格が異なるからです。
ですが、ILPがあれば、
ビットコインブロックチェーン→ライトコインブロックチェーン
というように直接・即座に取引が可能です。
中央集権的な取引所を通さなくなるので、マウントゴックス事件のように取引所がハッキングされるリスクはなくなります。
目次マウントゴックス(MtGox)とはマウントゴックスが破綻した経緯マウントゴックス事件のその後マウントゴックス事件のビットコインへの影響マウントゴックス事件まとめ マウントゴックス(MtGox)とは マウントゴックスとは、2009年に当初トレーディングカード(マジック・ザ・ギャザリング)の交換所として設立されたが(社名はMagic The Gatheringの頭文字MTGに由来)、2010年に暗号資産(仮想通貨)事業に転換して以来、一時は世界で取引量1位を誇った日本のビットコイン交換所です。 交換所なので暗号資産(仮想通貨)同士の取引を行っていたわけではありませんが、ビットコインを円・ドル・ユーロで購入でき、世界中に12万7千人のユーザーを持っていました。 2013年4月には世界のビットコイン取引量の70%を扱っていたこの交換所ですが、2014年には破産に至っています。マウントゴックスになにがあったのか、そしてその影響がどのようなものであったか見ていきましょう。 マウントゴックスが破綻した経緯 マウントゴックス事件の概要 2014年2月7日、マウントゴックスはビットコインの払い戻しを停止し、のちにマウントゴックスが所持していた顧客のビットコイン75万BTC(当時の価格で470億円相当)と預り金28億円、自社のビットコイン10万BTCが消失したことが判明しました。 このビットコイン消失事件がいわゆる「マウントゴックス事件」です。顧客への払い戻しのために巨額の負債におわれた結果、2014年2月にマウントゴックスは東京地裁に民事再生の申請をしました。しかし、申請は棄却され2014年4月から破産手続きが始まり、翌年には親会社のティバンも破産しています。 ビットコインの払い戻しは2013年ごろから遅延があったようで、その頃からビットコインが盗まれていることに気が付いていたにもかかわらず、マウントゴックスは操業を続けていたのではないかと懸念されています。CEOのマルク・カルプレスは2014年2月23日に辞任していたことものちにわかっています。 この事件をきっかけにあるべき資産がなくなることを「(マウント)ゴックスする」などと表現するまでになりました。 では、いったいなぜこんなことが起きてしまったのでしょうか? 犯人は社長?
銀行ネットワーク
様々な銀行の決済システムネットワークです。
現在、リップル社が銀行等にxCurrentというプロダクトを提供しています。
実際に、タイのKrungsri銀行で使用されており、これからもさらにxCurrentを採用する銀行が増えていくと思われます。
PayPalなどのモバイル決済ネットワーク
PaypalやWebpay、LinePay、中国で普及しているWeChat PayやAlipayなどがモバイル決済ネットワークに含まれます。
また現在、W3CがGoogle、Apple、Microsoft、Mozilla、Facebookと共同でブラウザAPIを開発しており、ここでもILPが応用されています。
※APIとは”Application Programming Interface”の略称で、簡単に言うと「ソフトウェアの機能を共有すること」です。
クレジットカードのポイントなどのネットワーク
楽天カードの楽天ポイントなど、クレジットカードを使ってショッピングをすると貯まるポイントや電子通貨が流通するネットワークです。
従来、これらのポイントは限定的な使い方しかできませんでしたが、ILPで他の価値と交換することで、より幅広い決済に対応できるようになります。
以上の4つの台帳がILPに接続されると、
- 取引所を使わずに、ビットコインでイーサリアムが買える!
- ビットコインで電子通貨にチャージできる!
- クレジットカードのポイントでビットコインが買える!
といった様々な価値交換が安全・高速・低コストで行えるようになります!
ILPの仕組み
ILPの仕組みを図解していきます。
リップルの開発者である「Stefan Thomas」と「Evan Schwartz」がYouTubeにILPの解説動画をアップしてくれています。ですが、動画は英語ですので、わかりにくいと思います。
動画の中の図を使いながら、解説していきます!
送金者、仲介者、受金者、そして「エスクロー」

上の図を見てください。
登場人物はそれぞれ
- 送金者=ユーロ圏のAlice(赤、左)
- 仲介者=Chloe(青、真ん中)
- 受金者=USドル圏のBob(緑、右)
です。各登場人物をつなぐ灰色のマークは「台帳」を表しています。
いま、送金者が100ユーロを仲介者を通じて送金し、受金者が100ドルで受け取るという国際送金を考えています。
具体的な手順は、
- 送金者のレジャーから100ユーロがクロエのレジャーに移動する。
- 仲介者のレジャー内で100ユーロが110ドルに両替される。
- 仲介者のレジャーから110ドルが受金者のレジャーに移動する。
となります。

しかし。上の図のように仲介者=クロエが100ユーロを持ち逃げしてしまうリスクがあります。
このセキュリティ上の問題を解決するために、「エスクロー」が登場します。
エスクローにはどのような役割があるのでしょうか。

エスクローとは、「商取引の決済に際して、中立的な第三者を通じて決済を行うことにより、安全な取引を保証する取引形態」のことで、「第三者預託」とも言われます。
それでは、エスクローがどのように機能するのか見ていきましょう。

↑ 送金者の100ユーロが一時的にエスクロー口座に送られます。このとき、まだ仲介者にはお金は渡らないので、先ほどのような仲介者がお金を持ち逃げするリスクはありません。

↑ 仲介者は送金者の100ユーロを受け取る前に、まず一時的に110ドルを受金者側のエスクロー口座に送ります。

↑ まず、エスクローが「仲介者が受金者へ110ドルを送金する準備ができていること」を確認すると、実際に送金が行われます。

↑ そして、エスクローが「送金者が受金者へ100ユーロを送る準備ができていること」を確認すると、実際に送金が行われます。

↑ これで、すべての送金が完了しました。
エスクローのおかげで、トラストレスな送金が可能になりました。
以上が、ILPによる送金のイメージです。
3つの送金モード
上で説明した送金方法はILPの「ユニバーサルモード」と言われます。
これ以外にも3種類の送金モードがあるので、ここで紹介します。
オプティミスティックモード
オプティミスティックモードは、全ての参加者が信頼できるという前提で行われています。
セキュリティ的に問題があるので、テスト環境以外で一般的に使われることはありません。
ユニバーサルモード
ユニバーサルモードではトラストレスな送金が可能です。
このモードでは、上で解説したお金の流れを逆にすることで、仲介者がお金を持ち逃げできないようにしています。
手順は、
- 仲介者がレジャー内にある110ドルを受金者に送る。
- 送金者がレジャー内にある100ドルを仲介者に送る。
となります。
これを可能にしているのが、HTLAs(Hashed-Timelock Agreements)という暗号学的に安全な送金の仕組みです。
ビットコインのライトニングネットワークで用いられているHTLCという仕組みがあるのですが、これを規格の異なる台帳間でも使えるように一般化したものがHTLAです。
途中で何らかの問題が生じて送金が滞った場合を想定して、タイムロック(時間制限)が定められています。一定期間の間に送金が実現しなければ、資金は元の保持者に返金されるような仕組みです。
このHTLAsにより、仲介者の信用にかかわらず暗号学的に安全に送金を行うことができるのです。
アトミックモード
アトミックモードでは、ユニバーサルモードとは逆に、信用できる第三者を承認者(バリデーター)として取引に仲介させる方法です。
手順は、
- 送金者がレジャーに資金をデポジットする。
- 受金者に送金する際にバリデーターの承認が必要。
となります。
アトミックモードでは、バリデーターの信用さえ得られれば、確実な送金を行うことが出来ます。
さらに、HTLAsという暗号学的な安全な仕組みを利用すれば、さらに安全性を高めることができます。
銀行などの金融機関では確実性を最重視するため、このモードが使われています。
また、リップルのxCurrentもアトミックモードを採用しています。
3つのモードとその特徴をまとめておきます!
3つのモードとその特徴
- オプティミスティックモード:全参加者の信用が前提。実用化はされない。
- ユニバーサルモード:HTLAsにより、トラストレスな送金を実現。
- アトミックモード:信用できる第三者(バリデーター)の存在により、確実な送金が可能。
4層からなる階層構造
では、ILPの仕組みを違う角度から見てみましょう。
次の図はILPの階層構造を示しています。

基本的な機能を提供するものは下層に、応用的な機能を提供するものは上層に配置されています。
下層から順番に4層からなる階層構造であることがわかります。
下から順番に、
- レジャー層
- インターレジャー層
- トランスポート層
- アプリケーション層
です。それでは、一つずつ説明していきます。
レジャー層
ILPでアカウントを作る場合は、レジャー層の実装が必須です。
レジャー層の役目は、それぞれの台帳と通信し、実際に送金を実行することです。
台帳によって、L1Plugin、L2Pluginなど様々です。
上でも説明した通り、ILPは主に4つの接続先が想定されています。
そこで、プラグインは、それぞれの台帳の仕様に合わせて機能を拡張するアダプターのように使われます。
その点で、プラグインはILPの真髄とも言えます!
インターレジャー層
レジャー層と同様に、アカウントの種類によらずインターレジャー層の実装は必須です。
インターレジャー層の役目は、送金に必要な情報を作成し、それを下層のレジャー層に渡すことです。
アカウントのアドレスを定義するILPと取引の見積もりを作成するILQPという2つのプロトコルがあります。
本来、ILPとはこのインターレジャー層のILPのことを指したものなのですが、ややこしいのでシステム全体を指して呼ぶことが多いです。
トランスポート層
送金者と受金者によって使われます。
トランスポート層の役目は、安全な送金方法を作ることです。
この方法には、PSKとIRP(Interledger Payment Request)という2つの方法がありますが、PSKのほうが安全なので推奨されています。
PSK(Pre-Shared Key)では、二者間でのみ共有される「鍵」を共有することで安全性を保っています。
アプリケーション層
トランスポート層と同様に、送金者と受金者によって使われます。
アプリケーション層の役目は、送信先を発見し、安全な通信を確立することです。
代表的なアプリケーション層のプロトコルにSPSP(Simple payment Setup Protocol )があります。
SPSPは送金者と受金者の間の安全な通信を確立します。
この通信はHTTPSにより暗号化されているので情報漏洩の心配がありません。
トランスポート層で作成された共有鍵が、このアプリケーション層に送られて安全に共有されます
まとめると、共有鍵により送金者と受金者を特定し、HTTPSという暗号通信で安全なやり取りを確立することで、詳細な情報交換ができるようになる、ということです。
以上の4つの層を通じて、送金者・仲介者・受金者へ送金の準備を行わせ、完了次第送金が実行されていきます。
4つの層とその機能をまとめておきます!
4つの層とその機能
- レジャー層:プラグインにより各台帳と通信し、送金を実行する。
- インターレジャー層:送金に必要な情報を作成し、仮想のレジャー層へ渡す。
- トランスポート層:PSKで作られた送金者と受金者の「共有鍵」を用いて、安全な送金方法を作る。
- アプリケーション層:送金者と受金者を特定し、安全な送金方法を確立する。
Q&A
ILPにXRPは利用されるの?
「世界中の銀行等に注目されるリップル社の技術はすごいが、XRPが使われるかどうかはまた別問題」というのはよく言われていることです。
この点について、リップルネットワークの開発者の一人であるDavid Schwartz氏は次のように述べています。
「このようなアプリケーションでXRPが機能するように『つくる』ことがリップル社の収益モデルになっている」
では、ILPの場合はXRPは利用されるのでしょうか?
ここで、先ほどの図をもう一度見てみましょう。

破線で表示されているコネクター(仲介者)がありますね。つまり、ILPは複数のコネクターの存在を前提としています。
たとえば、上で説明したようにアリスからボブへユーロをUSドルに換えて送金するような場合は仲介者はクロエの一人で十分でした。
では、コンゴ共和国のコンゴ・フランとインドネシアのルピアのようなマイナー通貨同士ならどうでしょう。
おそらくこの通貨間の流動性は低いので、他の通貨を、すなわち他の台帳をいくつか経由しなければ取引できないでしょう。
すると仲介者も増えていき、送金時間も仲介者が受け取る送金手数料も増大してしまいます。

これではILPのメリットをつぶしてしまっています。
ここで、高い流動性のXRPがILPを加速させます!
リップルをブリッジ通貨として挟めば仲介者の増加は最低限に抑えられるはずです。
現在、ILPが本格的に導入されているxCurrentではまだXRPは利用されていません。
ですが、実際にXRPが利用され始めたら、その価値は想像以上のものとなるでしょう!
ILPとアトミックスワップはどう違うの?
アトミックスワップとは、「異なるブロックチェーン間で取引を行う方法」です。
実際にアトミックスワップでも用いられている技術がILPでも使われています。
現在、ビットコインーライトコイン間、ビットコインーイーサリアム間での実験的アトミックスワップは実現しています。
異なるレジャー間での送金を可能にするという点では似ていますが、目指している方向性が異なります。
アトミックスワップは暗号資産(仮想通貨)間でのブロックチェーンでのみ適用され、暗号資産(仮想通貨)の経済圏を一つにまとめようとしていると言えます。
一方、ILPはブロックチェーンに限らず、金融機関などのネットワークを含め様々な規格の台帳を繋ごうとしていて、価値の標準化に徹しているとも言えます。
ILPとアトミックスワップはどちらも重要な技術です。
これらの違いを理解しておくことは大切です。
ILPまとめ
いかかでしたか?
ILP(インターレジャープロトコル)とは「異なる台帳間で価値の移動を行うための規格」でした。
世界中のあらゆる価値がILPによって繋がれば、すごい未来が見えてきます。
今後も、リップル社の動向に注目していきましょう!