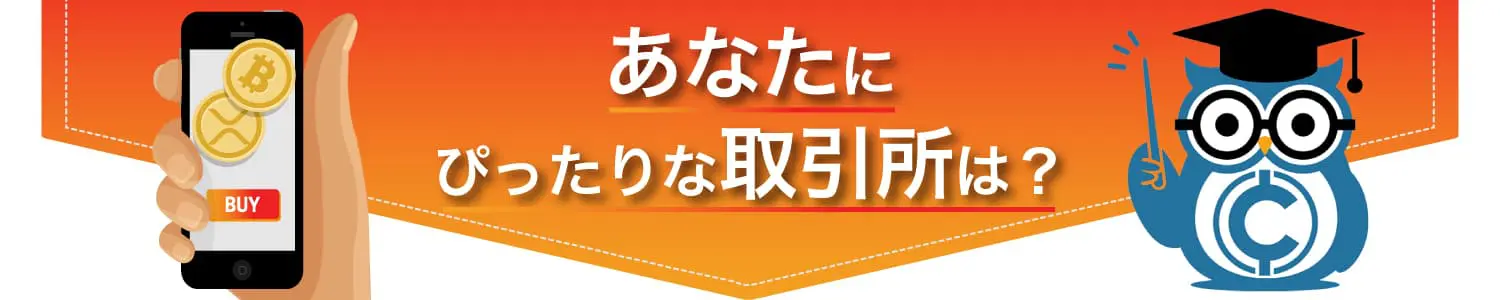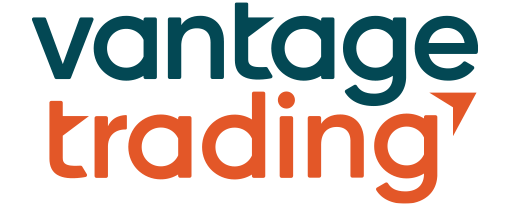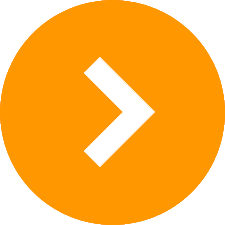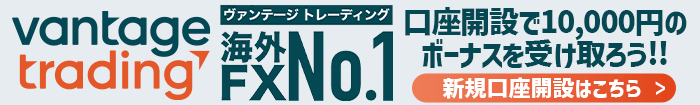ビットコインは国家を超える【定期コラム】

こちらの文章は先日M&Aでグループ会社となったBeat Holdings Limited社CEOの松田元氏によるコラムとなっています。
今後は松田氏と議論を重ねながら仮想通貨に関する見通しについて、定期的に連載していく予定です。また、松田氏はnoteによる解説も行っているので、是非そちらもご覧ください。
今回のコラム概要
タイトルにもある通り、「ビットコインは国家を超えることができるのか」というところが今回のコラムの中核となります。
ビットコインの人気ぶりは衰えを知ることなくうなぎ登りです。
仮想通貨の主役は今も昔も、そして今後もビットコインであり続けることは間違いないでしょう。
そのビットコインの将来を探るにおいて、ブロックチェーンや、政治や通貨との関係性にも触れています。
そして、ビットコインとリブラの関係が金とダイヤモンドの関係と同じであることをあげ、ビットコインの可能性についてとことん解説しています。
ブロックチェーン技術の問題点
識者は皆、ブロックチェーンの技術的可能性に大変期待をしているものの、その特性故、“社会秩序”とどう併存させるかが、とにかく定着に向けた最大の論点だと認識をしています。
つまり、匿名性が担保された完成度の高い民主主義の技術であるが故に、51%リスク(51%のノードをアタック、乗っ取られて、民主制が崩壊するリスク)の回避の仕方、アンチマネーとの融和回避、保証者(通常は国家)不在の有事対策、などなど、特異なリスクとどう向き合うか、が規制当局の最大関心事のようです。
全ての物事が完全民主主義で決議されたとして、実はその民主主義がダミーノードで決議されていたり、あるいは反社会勢力の影響を受けて決議されていたとき、技術としては完全に民主的な決議がなされたとて、それは人類の未来にプラスの事象であるのか、と言われれば、答えに窮するのが通常です。
悪魔の証明
一方で、
じゃあ国家が嘘をついていない根拠は何だ?選挙は本当に平等なのか?何故今日び、紙と鉛筆で書かせるんだ?改ざんと不正温床なんじゃないか?
と言われれば、『陰謀論者め!』と多くの知識人の共感を生む一言で一掃することは出来ます。
しかし、実際に国家が嘘をついていない証拠を出すのは、悪魔の証明(証明することが物理的に不可能な事象の総称。魔女狩りを例にとると、魔女ではないことを証明するには死ぬしかないため、生存時に魔女ではないことを証明することが不可能)となってしまうので、これもまた非常に難しいわけです。
要するにこれは、民意を信用するのか、国家を信用するのか、という、極めてプリミティブ(原始的)政治的思想に直結していくわけです。
そして、更にややこしいのが、この完全な民主主義を実現しうる技術が、“トークン”なる魔法によって通貨圏まで構築できてしまうという点にあります。
政治と通貨
政治はもちろん政治として固有のシステムがあるわけですが、その基盤となっている思想は資本主義であり、資本主義は貨幣が主役で、その貨幣を発行する通貨発行権は国家の最も基幹的な機能です。
通貨の信用が高ければ金利が下がり、金利が下がることで資金調達コストが下がり、国家としての競争優位性が増していきます。
通貨というコントロールマスター(神)がいるからこそ、国民は安心して民主主義を信じることができ、選挙に行き、安心して投票できるわけです。
その通貨、あるいは通貨が取引されるマーケットが、
あれ、これって大丈夫なんだっけ?
と疑義を抱かれるようになると、例えば“金”や“日本円”のような安全資産とされる対象に資金が移動します。
最近でいえばリスクオフアセットにカウントされつつあるビットコインなど暗号通貨(資産)にも、資金が流入してくるわけです。
特に最近の相場では、(政治手腕や圧倒的カリスマ性などは置いておいて)一国の大統領のツイッターの一言でマクロ相場が仕手株並みに激しく(10%近く)変動するという、市場原理をほぼ無視した異常事態(末期症状)が発生しているわけです。
通貨とは何か、国家主権とは何か、そして民主主義とは何かを、根本から疑いたくなる気持ちはよーくわかります。
結局のところ
さはさりながら、暗号資産は一部国家の認可事業として認知されてしまっています。
そして米規制当局(SEC)も世界の暗号資産に広く網掛けをしてしまっています。
つまり、その意向を無視して事業を推進することは現実性がありません。
匿名性の高い完成された民主主義を、しっかりとしたKYC/AML/CFT(アンチマネー対策)をセットにして、ブロックチェーン技術で実現していく
という、なんだか分かったような分からないような不可思議な言葉で表現せざるを得ないのが現状です。
これは日本に限らず、シンガポール、香港、マレーシア、米国、そしてロンドンなどのブロックチェーンプレーヤーも同じです。
ブロックチェーンは素晴らしいけどKYC/AML/CFT(アンチマネー対策)は必須だよね、という論調にあること、アナーキー(無政府主義者)が跋扈する市場から、着々と成熟した産業に進化していることはグローバルに見ても間違いありません。
でも、立場的にも論理的にも突き詰めて考えればもちろんそうなのですが、一方でビットコインやブロックチェーンという、未来からやってきたスペシャルなオーパーツがこれまでの国家中心資本主義の課題を、
“ミラクルな発想で”根底からひっくり返してくれるんじゃないかな
という、根拠レスな淡い期待や夢もあります。
これは小職含めてブロックチェーンのもたらす膨大な可能性(それを人類は、次世代で新たな神と呼ぶのではないでしょうか)に、ブロックチェーンプレーヤーがかなり毒されているのではないでしょうか。
頭では社会秩序とその対策をしっかりと講じて事業を進めることが最優先と分かっているのに、ビットコインが何かHeroicに見えてしまうのは、ビットコイン症候群とでも呼ぶべきものなのかもしれません。
ビットコインは国家を超える
そんなことを考えていたとき、ふとビットコインとリブラの関係が、“そうか、これは金とダイヤモンドの関係と同じなのか”、ということに気づきました。
もちろんビットコインは金であり、リブラ(あるいはXRP、あるいはまだ見ぬアルトコイン)がダイヤモンドです。
詳細は本稿の趣旨ではありませんので割愛しますが、ダイヤモンドはデビアスという企業が独占して価格を決めており、たった100年足らずで、単なる炭素を、恐ろしい規模の世界市場に昇華させた経緯があります。
一方で金は、埋蔵量が決まっていて、地球にその数の上限もあり、価値が一定以上担保されてきたという歴史があります。
(金価格もまた、ロスチャイルドグループの一部権力者が毎回価格を決めているという説もありますが、話がややこしくなるのと小職の専門ではないのでここでは割愛致します)
デビアスがダイヤモンド価格を決めることがフリーハンドで許されていれば反トラスト法で即処罰されるわけです(過去何度か事例はあったようですが)。
そして、やはりダイヤモンドもまた、デビアスに価格を決められるうえで、何らかの社会秩序の保証に向けて、等価交換をしているわけです。
つまりこれは、リブラが残り数年で世界通貨に進化するにあたり、KYC/AML/CFT(アンチマネー対策)が必須機能として備わることが、ダイヤモンドにおけるデビアスのような存在になるターニングポイントとなるのだと思います。
まとめ
コインパートナーの無料オンラインサロン「Coin Learning(コインラーニング)」に登録してくださった方のみに、この記事の総まとめやこの記事を読んでくれた方に特に伝えたいことを配信しようと思います。
「ビットコインは国家を超える」のタイトルの意味がまとめにて明らかにされております。
Coin Lerningへ登録↓↓↓
松田氏について
Beat holdings limited(9399)CEO。早稲田大学商学部卒。実業家としての経験を活かし、複数の上場企業における投資銀行/バリューアップ業務を豊富に経験。2016年衆議院予算委員会における中央公聴会にて、最年少公述人として日銀の金融政策に関する意見を述べる。
投稿日時:
著者: CoinPartner 編集部 CoinPartner