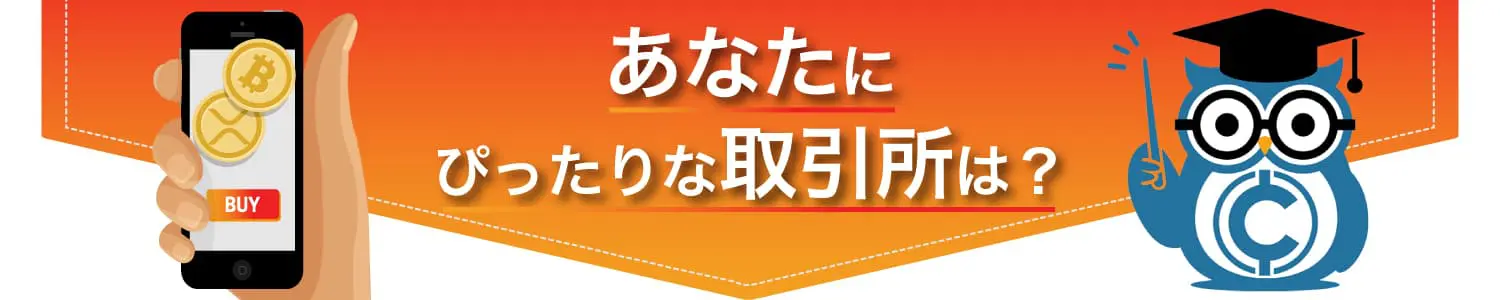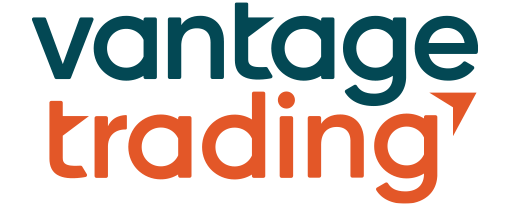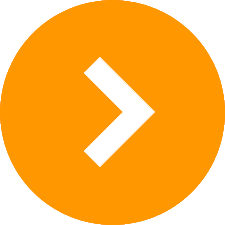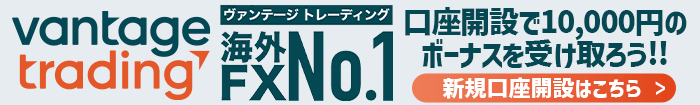バイナンス元CEO CZ、イーロンマスク氏にX上でのボット禁止要請

仮想通貨取引所バイナンスの元最高経営責任者(CEO)であるジャオ・チャンポン(通称CZ)氏が、イーロン・マスク氏の運営するソーシャルメディアプラットフォーム「X(旧ツイッター)」に対し、すべてのボットを禁止すべきだと発言しました。
CZ氏は、API投稿を無効化することで、プラットフォームの透明性と信頼性を向上させることを提案しています。
CZ氏の見解:AIの役割とボットの問題
CZ氏は、AIがホテルの予約、チケットの購入、コードの作成といった日常業務には有用であると認めつつも、AIエージェントと「交流」することには価値を感じていません。
彼にとって、ボットは単なるノイズであり、ユーザー体験を阻害する要因と見なされています。
特に仮想通貨分野では、ボットによる情報拡散が詐欺や市場操作を助長するリスクが高まっています。
これまでにも、多くのスパムボットが仮想通貨関連の詐欺を行い、有名人になりすましたアカウントが「無料配布(Giveaway)」を装った詐欺を展開するケースが報告されてきました。
さらに、ボットが市場の風説を操作し、特定の仮想通貨の価格を吊り上げたり、不安を煽って売却を誘導するケースも存在します。
X(旧ツイッター)のボット問題とマスク氏の対応
イーロン・マスク氏は、X(旧ツイッター)の買収前からボット問題に取り組んできました。
しかし、現状ではこの問題はさらに悪化していると指摘されています。
特にX(旧ツイッター)の財務モデルの影響により、有料の「青いチェックマーク」を取得したボットアカウントが増加し、ボット同士が「いいね!」やリプライを送り合う「ゴーストタウン」のような状況が生まれています。
サイバーセキュリティ企業CHEQの調査によると、X(旧ツイッター)のトラフィックの大部分が偽物であると判断されており、ボットの作成が一つの産業として確立されつつあることが明らかになっています。
特にAIによるスパムコンテンツが急増し、ユーザー体験を大きく損なっています。
マスク氏はこの状況を改善するために、X(旧ツイッター)上での投稿ごとに少額の料金を課すアイデアを提案しました。
この方法により、ボットの乱用を抑制しようとしましたが、当時この提案には強い反発があり、実施には至っていません。
CZ氏とマスク氏の関係性
興味深い点として、2022年にマスク氏がツイッター(当時)を買収しようとした際、CZ氏は5億ドルを出資していました。
この出資について、CZ氏は2023年12月に「この大義に貢献できて嬉しい」とコメントしています。
しかし、今回のボット禁止要請は、X(旧ツイッター)の現状に対する懸念から発せられたものであり、CZ氏がプラットフォームの品質向上を求めていることが伺えます。
ツイッター上のボットによる仮想通貨関連のトラブル
ツイッターは、仮想通貨に関する情報共有や議論の場として広く利用されています。
しかし、そのオープンな性質を悪用し、ボットを利用した詐欺やスパム行為が横行しています。
例えば、2018年の調査では、仮想通貨の無料配布を装った詐欺アカウントが約15,000個存在することが明らかになりました。
これらのボットは、有名人になりすまして偽のキャンペーンを展開し、ユーザーから個人情報や資産を騙し取る手口を用いています。
さらに、2022年には、仮想通貨コミュニティ内で「なぜ誰もこれについて話していないのか」といったフレーズを用いるスパムボットが増加し、健全な議論を妨げる事態が報告されています。
これらのスパムボットは、怪しげなプロジェクトや詐欺サイトへのリンクを拡散し、ユーザーを誘導することで被害を拡大させています。
フェイクフォロワー問題と信頼性の低下
仮想通貨関連のインフルエンサーや企業アカウントのフォロワーの中には、フェイク(偽物)が含まれていることも問題視されています。2023年の調査によれば、シバイヌ(SHIB)の公式アカウントのフォロワーの約10.26%がフェイクアカウントであることが判明しています。
このようなフェイクフォロワーの存在は、アカウントの信頼性を損ない、情報の正確性や透明性に疑問を投げかける要因となっています。
イーロン・マスク氏の呟きに便乗した仮想通貨ボット問題
X(旧ツイッター)のオーナーであるイーロン・マスク氏自身も、ボット問題に直面しています。
彼のツイートに関連して、ボットアカウントがアルトコインの価格に影響を与えるケースが報告されています。
また、マスク氏が特定のボットアカウントを「詐欺仮想通貨アカウント」と指摘し、凍結させた事例もあります。
これらの事例は、ボット問題の深刻さと、その対策の必要性を浮き彫りにしています。
考察:X(旧ツイッター)の未来とボット問題解決策
X(旧ツイッター)のボット問題は、仮想通貨業界だけでなく、あらゆる分野に影響を与える重大な課題です。
ボットの存在は、詐欺や市場操作だけでなく、プラットフォーム全体の信頼性を損なう要因となっています。
CZ氏の要請は理にかなっていますが、現実的にはAPI投稿の完全禁止は難しいでしょう。
X(旧ツイッター)の開発者や正規の企業アカウントにとってAPIは不可欠であり、無効化すれば正規ユーザーにも影響が出る可能性があります。
また、マスク氏の提案した「投稿ごとの課金」は、確かにボットの運用コストを上げる効果はあるものの、一般ユーザーにとっても負担となるため、採用は困難です。
今後の解決策としては、以下のようなアプローチが考えられます。
ボット検出アルゴリズムの強化
AIを活用してボットアカウントを検出し、自動的に排除するシステムを導入します。
ユーザーの認証強化
アカウント作成時の本人確認を厳格化し、ボットの作成を防止します。
APIの制限強化
企業や開発者向けのAPIは維持しつつ、不正利用を防ぐための制限を追加します。
レポート機能の改善
ユーザーがボットを迅速に報告できるシステムを強化します。
まとめ
バイナンス元CEOのCZ氏は、X(旧ツイッター)におけるボット問題の深刻さを指摘し、API投稿の無効化を含む抜本的な対策を求めました。
一方、X(旧ツイッター)の運営者であるイーロン・マスク氏も長年この問題に取り組んできましたが、現状ではボットの氾濫が悪化しているのが実情です。
仮想通貨業界において、ボットは詐欺や市場操作を助長し、投資家の信頼を揺るがす要因となっています。
X(旧ツイッター)の未来にとって、ボット対策の強化は不可避であり、単なる規制ではなく、AIの活用やユーザー認証の厳格化など、多角的なアプローチが求められます。
マスク氏とCZ氏という二大影響力者の発言をきっかけに、X(旧ツイッター)がどのように進化し、仮想通貨市場全体の健全化に貢献できるか、今後の動向に注目が集まっています。
投稿日時:
著者: CoinPartner 編集部 kishimoto